引っ込み事案な人が作業療法士になるまで 現役教員が2つの方法を伝授
公開日:2023.02.17
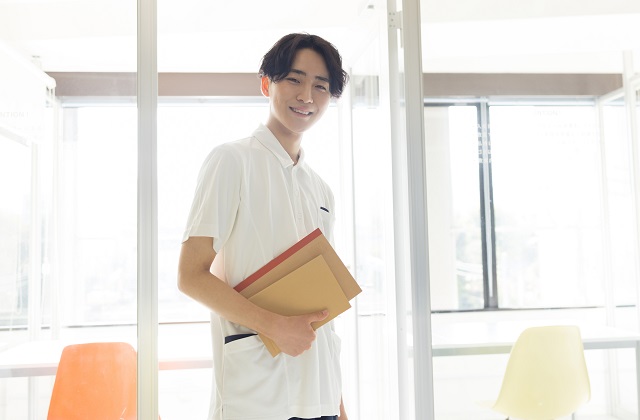
文:泉良太(作業療法士)
私は作業療法士の養成校で教員をしていますが、本学に通う学生を見ていると、「気持ちは優しいけど、シャイで引っ込み思案」といった印象をもちます。
作業療法士は対人援助の仕事ですから、それなりのコミュニケーション能力が備わっているように思うかもしれませんが、実際は「人助けをしたい=人と接するのが得意」というわけではないようです。
では、引っ込み思案な人が、コミュニケーション能力を必要とする作業療法士になるにはどうしたらいいのでしょうか。
ここでは筆者の教員としての経験も交えながら、その方法を考えてみたいと思います。
引っ込み思案な学生も一人前になっていく
まず強調したいのは、引っ込み思案な学生であっても、大多数は最後にはしっかりと一人前の作業療法士になっていくことです。
入学したばかりの学生は、他者貢献をしている自分の姿から自己効力感や自己肯定感を満たしたいという心理があったり、親や高校の先生の勧めで進学先を決めたり、とりあえず手に職が欲しいなど、自分の欲求をはっきり捉えられていない方もいます。
ところが、そうした学生たちが未成熟な自分と向き合い、学校生活や現場実習などを通してさまざまなことを経験すると、やがて「1人の大人」に成長していきます。その姿はなんともドラマチックです。
作業療法士になることにイマイチ自信が持てなかった学生も、しっかりと変わり成長していくのです。
では、そのためには何が必要なのでしょうか。
10~20代は不安定が当たり前
具体的な方法の紹介の前に、10~20代の特徴を改めて紹介したいと思います。
発達心理学では、10代から20代前半は「混乱の時期」といわれています。10代前半は友人関係をとおして他者意識が強まり、自己評価が不安定になります。10代後半から20代前半は少しずつ親元から離れ、社会を担う存在として責任と関与が求められる立場へと変化します。
このような年代を駆け抜けながら、「自分は何者であるのか」「自分は世の中で存在価値はあるのか」など自問自答を繰り返して、不安と期待が交錯するのがこの時期です。そのため、やりたいことが定められなかったり、本当に自分に合っているものが何のかわからなかったりするのは当たり前なのです。
自分の人生に自信がもてず、不安になって引っ込み思案になるのも、ある意味致し方のないことでもあるのです。
自分を受け入れることで成長の扉が開く
ではここから、引っ込み思案な自分を変える具体的な方法をお伝えしたいと思います。
1つ目は、「自分を受け入れること」です。
コミュニケーション能力が足りなくてもシャイであっても別にそれはそれでいいのです。そうした自分をしっかりと受け入れ、そこからどうやって一歩前へ踏み出すかが大切なのです。
以前、実習へ行っても数日で帰ってきてしまう学生がいました。理由を聞いてみると、「中学時代は痩せていて、サッカーが上手だったけど今は違う」と打ち明けました。現在の彼は太っていて、輝いていた過去の自分と比べて苦しんでいたのです。
一見、実習とは無関係のように見えます。ところが彼は、現在の自分がどうしても受け入れがたく、どこへ行っても自信がもてませんでした。だから、実習に行っても自信がもてずに数日で帰ってしまうのです。
そこで面談を何度も重ね、過去の自分を紐解きながら少しずつ一緒に自分自身と向き合う作業をしました。その結果、今の自分を受け入れられるようになり、自信も少しずつついてきました。その結果、彼は今、夢であった精神科の作業療法士として立派に働いています。
ただ、ここで強調したいのは、「受け入れること」と「開き直ること」は違うということです。
開き直りはその場に留まるだけであまり成長は期待できません。私の経験上、一番スムーズかつ持続的に成長を続ける学生の多くは、素直に自分を受け入れた方です。
そしてその先には、変なプライドも怖さもない、ありのままの自分を受け入れたがために感じられる「すっきりとした自分」が存在しているように見えます。
生体験が必要
引っ込み思案な自分を変える2つ目の方法は、「生の体験」です。
今の学生はTwitterやInstagramなどのSNSをよく使います。それによってさまざまな人間関係ができると思いますが、SNSだけでは足りないものがあると思います。それは「五感」です。
例えば、SNSでおいしそうなパスタの投稿をしても、見た人は視覚しか刺激されません。
これがもしお店なら、大きさや形状がもっとリアルにわかり、匂いや食べたときの食感や味、温度、店内の音、友達と交わした会話や店員さんの雰囲気など、数えきれないくらいの情報が自分の中で広がっていきます。そして、それらの情報が統合されて「あのパスタ」という認識になります。
コロナが流行する前ですが、こんな話がありました
私が教員を務めている学校の1年生を対象に、近隣の有料老人ホームや保育園でコミュニケーション体験をするプログラムを実施していました。
授業でお年寄りや子どもの特性とコミュニケーションの基本を学び、現場に行って実践して、学校に戻ってから振り返りをするというサイクルを年間で8回ほど行いました。
はじめは恥ずかしさや緊張があったものの、回を重ねると、消極的な学生も現場経験を重ねるとそれなりに慣れてくるものです。
そのなかで印象に残っている1人の学生がいました。勉強はできるけどプライドが高く、傷つくことを避けがちな男子学生でした。
その彼が保育園実習当日の朝、「俺、子どもが苦手なんです」と言っていました。
ところが、2時間ほど子どもたちと公園で遊ぶと、最後はたくさんの子どもたちと手をつないで活き活きとした表情で園に戻ってきたのです。
私が「朝言っていたこと違うじゃん」とツッコミを入れると、男子学生は「以外と大丈夫でした」とはにかんでいました。
先ほどの「パスタ」の例のように、生体験をとおして外界(社会)に存在するありとあらゆる情報をひとかたまりに統合していく作業は、自分の価値観を見直して整理することになります。
スマホ片手に情報が手に入るのはとても便利ですが、自己の確立にもがいている10~20代の時期には、このような、生の体験が必要だと強く思います。
学校は生体験の連続
冒頭で作業療法士を目指す学生の印象を、「気持ちは優しいけど、シャイで引っ込み思案」といいましたが、これは彼ら特有の性質ではなく、若者は誰も似たり寄ったりなのかもしれません。
今回私が述べたことは作業療法士という仕事だけでなく、若者に共通した特性でもあります。ですから、自分が作業療法士という仕事に惹かれたのであれば、適性にあまりこだわらず、その気持ちに従って進めばよいと思います。そこでポイントは、自分を素直に受け入れること、そして生の体験をたくさんすることです。
作業療法士になるためには養成校へ3~4年間通います。専門的な授業、クラスメイトや教員との交流、現場での実習など生の体験の連続です。入学時は作業療法士をなぜ選んだのか、そもそも自分とはいったい何のかわからない学生たちも、卒業のころには自分の手綱をしっかりと握って巣立っていきます。
時にはつらいこともありますが、作業療法士の資格だけでなく、自分の力で歩いていける強さも身につけていただけたらと思います。

泉 良太
音楽の専門学校を卒業後、2007年に作業療法士の資格を取得。
都内リハビリテーション病院、救急病院で主に脳卒中に対する作業療法に従事。2015年より東京福祉専門学校の専任教員。
修士(医療福祉教育・管理学)。博士課程在学中。
他の記事も読む
- 【理学療法士の本音】苦手と感じる患者さんの特徴とは?苦手な患者さんへの対処法について解説
- ブランクがある作業療法士必見!不安を解消して復帰するための職場の選び方を紹介
- 【現役STが解説】言語聴覚士に向いている人はどんな人?適性や向かない人の特徴
- 頸椎椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?なりやすい人の特徴やセルフケアについて解説
- 五十肩でやってはいけないこと4選!自宅でできる対処法もあわせて解説
- 訪問リハビリテーションの給料相場はどのくらい? 仕事内容や求人を探すポイントについても解説
- 作業療法士は無資格でもなれる?助手として働く選択肢や免許を取る方法など現役作業療法士が解説
- 【言語聴覚士が解説】自宅でできる構音障害のリハビリ方法7選!
- リハビリは特掲診療料に含まれる!施設基準や算定できる加算などについて現役作業療法士が解説
- バネ指とは?原因や症状、やってはいけないことについて解説
- 20代理学療法士の給料相場は?他職種との比較や給料アップの方法を解説
- 側弯症の人がやってはいけないこととは?側弯症の種類と症状を解説
- クローヌスの止め方とは?原因のほか家庭でできる対策と医療機関での治療も紹介
- 言語療法士と言語聴覚士の違いは?ST・PT・OTとの違い・資格を取得するための方法も解説
- セラピストの仕事はしんどい?理由ややりがい、向き不向きを現役作業療法士が解説
- 「セラピストはやめとけ」は本当?セラピストの退職理由や向いていない人の特徴を紹介
- セラピストが仕事に抱く本音は?業務内容や待遇、人間関係の現状について現役作業療法士が解説
- たんぱく質を摂り過ぎているときのサインとは? 摂り過ぎないポイントも解説
- 進行性核上性麻痺の人のリハビリや日常生活における注意点を現役作業療法士が解説
- ケアカンファレンスとは?記録の書き方や関わり方のポイントを徹底解説!





















