リハビリ3会長鼎談: 始動する地域包括ケアシステム リハビリの目標を問い直す
公開日:2018.06.29 更新日:2018.07.09
医療の機能分化と地域包括ケアシステムの本格的始動が織り込まれた2018年度診療報酬・介護報酬改定。リハビリにも合理性・科学的根拠が求められる時代に、セラピストが直面する課題とは? 前回に続き3協会長本音の鼎談(ていだん)をお届けします。

参加者(敬称略)
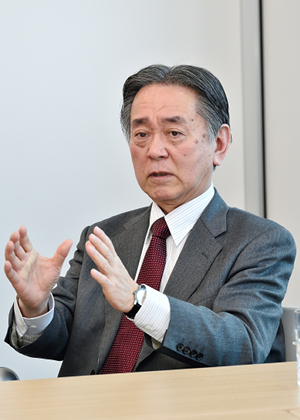 |
 |
 |
 |
 |
| 半田一登 | 中村春基 | 深浦順一 | 中保裕子 | 横河麻弥子 |
|---|---|---|---|---|
| 公益社団法人日本理学療法士協会 会長 |
一般社団法人日本作業療法士協会 会長 |
一般社団法人日本言語聴覚士協会 会長 |
医療ライター (司会) |
マイナビ「セラピストプラス」編集 |
所属:2018年6月現在
「在宅復帰」させるだけでいいのか
中保(司会) 今年(2018年)の診療報酬・介護報酬同時改定では、地域包括ケア推進の流れから在宅復帰率が重視されています。
中村(OT) 活動・参加、自立支援がうたわれながら、大きな指標は在宅復帰率と実績指数であり、単位数でしか見ていない。自立支援というのは、本来その方が退院した後にどのようにその人らしく生きているかという、QOL(生活の質)の視点が入るべきだと思うのですが。
深浦(ST) 私も社会に戻っていく場合の参加の仕方、復帰の仕方が問われるべきだろうと思います。私は学校の教員でもあるのですが、学生たちの臨床実習で書かれる目標に「在宅復帰」と書いてあるだけが多い。私は「在宅復帰するのは当たり前だろう」と話しています。職場復帰にしても、どういう職場でどう今までの仕事ができるのか、どのようなサポートを受けながら職場に復帰するのかを考えないといけません。リハビリテーションの提供がパック化された中で、それを考えられる療法士が育っていかなくなると危惧しています。ですから、一人ひとりの患者さんに対してあるべきオーダーメイドのリハビリテーションの提供がきちんとできているかどうかが評価されるべきだろうと、最近は強く思うようになりました。

半田(PT) リハビリテーションの本来の目標は、在宅ではなくて社会に帰すことです。平成18年までは、「家庭復帰」とは社会復帰ができないから家庭復帰としただけで、リハビリテーションとしてはいわば負けゲームでした。それがいまは評価の軸になっている。家に帰って寝ているだけでも、在宅復帰。評価軸がそこまで下がってきているということを、我々3職種は重大に捉えていかなければなりません。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の使命は患者さんを社会に帰して、学校や仕事、社会参加といった元の生活をどのようにしてもう一度送っていただくかにあります。高齢社会の影響でしょうが、在宅復帰はリハビリテーションの本質ではないと私は思います。
中村(OT) ここ10年ほどは国の掲げる「共生社会」や「一億総活躍」といった理念のもと、高齢者も在宅に戻るだけでなく地域社会でどのように生活するかということが問われています。ですから、リハ職も病院の中だけではなく、半田会長が言われたように「その人がその人らしく地域で生活ができるように」と、考えることが地域包括ケアシステムが取り組むべき課題です。今回の診療報酬改定はまさに地域包括ケアシステムに向けての大改定ですので、少しずつ前進しているような感覚は持っています。
いま必要なのは医師からの具体的な指示
中保(司会) 今回の介護報酬改定では、リハビリテーションマネジメント加算の要件に医師の詳細な指示が加わり、ICT(情報通信技術)による医師の地域リハビリ会議の参加など、医師のリハビリテーション関与の強化が示されています。
半田(PT) 平成27年度改定でリハビリテーションマネジメント加算ができた当初から、地域リハビリテーション会議への医師の参加が懸念されていたのですが、3年間やってみてやはりそれがネックになりました。ICTの活用はその対応策です。
これから地域包括ケアシステムや介護保険領域において、我々を存分に使って良い結果を出していただくためには、意欲があり、指示がしっかりできる能力がある医師がどれだけいるかによります。それによってまたPTも、OTも、STも育ちます。ぜひ、すばらしい指示を出して、一人ひとりの利用者、あるいは、患者さんが目いっぱいの能力を発揮して社会復帰できるようにしていただきたいと願っています。しかし、現実的には、まだまだ医師のリハビリに対する関心は薄いと感じます。以前の本会の調査によれば、病院のリハビリテーションの中での医師の指示が具体的な内容ではなく、単なる開始の指示となっているケースが全体の75%を占めていることがわかりました。ベテランの療法士にとっては自分の意思で組み立てられますが、新人療法士は「自由に」と言われたら目標がなくなり、育たなくなってしまいます。医師の関与は必要なことですが、しっかり具体化することが非常に大事だと思います。

深浦(ST) 言語聴覚療法では、医師と療法士の役割は明確に分かれます。聴覚障害を例にとると、治療は医師が全面的に責任をもち、我々は検査に参加します。2~3カ月で改善の見込みがわかりますので、そのままでは生活できないとなると言語聴覚士に回ってきます。補聴器にしても医師の指示は要りますが、その調整とか、聞き取りの練習などの関与の中心はSTです。脳血管障害ではちょっと違う側面はありますが、初期の治療的な観点のフェーズと、その後の生活機能や社会活動・参加を促進していく取り組みのときの責任の度合いは違ってくるのだろうと思います。リハビリテーション医の先生方がその境目のところあたりにおられるのですが、その先生方が人数的に多くないことが、現実的に移行がうまくできていない大きな要因だろうと思います。リハビリテーション医師の数が少なく、言語聴覚士の数も少ない。だから、もう少し役割分担をしないとサービスが十分提供できない。現在の数の中で何ができるかが重要な視点だと感じています。
「リハビリの科学化」のためにすべきこと
中保(司会) 今後の医療は、エビデンスに基づく診療の合理化、効率化が一層進められると思います。リハビリテーションにおいても科学的検証、エビデンスの集積が求められると思いますが、今後の「リハビリの科学化」をどのようにお考えでしょうか。
中村(OT) 平成18年に診療報酬の体系が障害別から疾患別になったときに、評価が「リハビリテーション料」で包括されてしまったことを問題だと感じています。STとOTが少ないために、同じ単位でも全てPTがやっている施設もあれば、PT、OT、STが分担している施設もある。PT、OT、ST、それぞれ対象も方法も全く違うのですが、それを全て一つのこととして評価されることにより、その違いが見えなくなってしまった。効率的な医療を考えるならば、理学療法と作業療法と言語聴覚療法それぞれの効果を検証していくべきです。そこのところは大きな課題として残っていると思います。

半田(PT) たしかに現在の診療報酬では、単位数の内訳が全くわかりません。それでは統計として一人の患者さんに、理学療法何単位、作業療法何単位が適切かというデータが出せません。本来の「医師の指示」とは具体的に施術の量と方法を命ずるものなのですが、それができなくなっています。リハビリをどう科学化するかというときに、データがないというのは最大の弱点です。「データヘルス」と言われている中で、理学療法、作業療法、言語聴覚療法がどう行なわれたかがつぶさに見えるように報酬も改定していただきたいですね。
深浦(ST) 言語聴覚療法の初期の研究には「言語聴覚療法は効果がない」という報告も結構ありました。それらの報告はただ「言語聴覚療法を行なった」だけで、具体的な内容を問うていないものでした。最近は、具体的な訓練法、指導法、治療法を示した上で、継続的に行なうと効果があるという報告がどんどん出てくるようになりました。方法論によって効果が違うものを丸めても効果は証明できません。エビデンスを出すためにはどういう介入をし、どういうデータをとるかを統一し、その結果を同じように判断するのは当然のことです。
それと、身体機能に比べて言語聴覚機能に対する評価はちょっと低くみられていると思っています。FIM(機能的自立度評価表)や日常生活動作を評価する方法の一つBarthel Indexでもコミュニケーションと食事の2項目程度しか出てきませんし、介護保険の重症度評価でも言語聴覚関連の項目はあまり多くないので、言語障害があっても要介護度は低く評価されてしまいます。
中村(OT) 作業療法の中では、一つひとつの技術に対して標準化を進めているところですが、その取り組みはより一層進めていく必要があります。例えば服を着るにしても、認知の問題、運動の問題といった要素が整理されないと効果が見えないわけです。その点では、理学療法の方がわかりやすい。作業療法は、一人ひとりの生活の中で、その人の体と様々な生活の背景と、環境も絡みますから。
中保(司会) それぞれの療法をきちんと分けて整理することが必要というのは、皆さん同じ思いでいらっしゃると。

深浦(ST) そうですね。そして、患者さんは1個人ですので、チームとしてどう対応するか。医師のイニシアチブとか、チームとしての目標に向かった協働が重要になると思います。
半田(PT) ただ、統計では人間を標本化しなければ、科学になりません。ところが、我々が診るのは一人ひとりの生活です。「一人の女性」ではなく「あなた」でないといけない。中村会長が言われたように、家庭環境も、家族も、社会的環境も全て異なる患者さんたちが全て標本化されてしまったら、リハビリテーションの一番の長所が見えなくなるという面もある。「リハビリの科学化」の難しさはそこにあると思います。
横河(編集) 個人としての人とデータとしての人、両方追わないといけなくなってきたのでしょうか。
中村(OT) そう、両方でしょうね。どちらも必要です。
(続く)

他の記事も読む
- 管理栄養士・栄養士2,129人が語る真実は?やりがいや働き方について大調査!
- 能登半島地震避難所で「介護人材」不足、体調悪化させる人が続出
- 「ピラティス」腰痛の治療・改善に効果か~徳島大学が全力で普及へ
- リハビリに革命!「仮想現実」を活用した県リハビリテーション病院の新プログラムが話題に
- 【能登半島地震対応】理学療法士が被災地へむけて遠隔支援開始~避難所でできる「リハビリ動画支援」
- 【整体に関するアンケート結果】整体・リラクゼーションサロンの10万施設が無資格運営~その実態を知っているのは僅か10.9%
- 2023年11月(月間)の人気職業ランキングを発表!~13歳のハローワーク公式サイト(13hw)から
- 子どもの「感覚」「動作」の困りを調べるサービスを開始
- 医療ドラマの新たな切り口 吉沢亮が月9で新境地を見せる『PICU 小児集中治療室』
- 作業療法士のキャリアパスを考えるYouTubeチャンネル始動!
- あの天才放射線技師&外科医が帰ってくる!秋の医療系ドラマに注目
- 訪問看護の理学療法士が語る「生活を支えるリハビリの魅力」
- アンソニー・ホプキンスが認知症の父親役を演じる映画『ファーザー』、5月14日全国公開
- 「呼吸リハビリテーションと運動療法」令和2年度リハ講演会レポート
- 新型コロナ禍で介護者の不安を減らすには?セラピストができるケア
- 新型コロナの影響で訪問リハビリはどう変わる?現状と今後について
- 在宅医療・介護をテクノロジーで支える――臨床経験者たちの挑戦
- withコロナ時代のセラピストの現状と今後の展望
- 知恵と雅~東京・港区で赤坂芸者衆登壇の感染症対策セミナーが開催
- 言語聴覚士の臨床実習ではどんなことをするの?新型コロナの影響についても
















