理学療法士の勉強内容は?ついていけないと感じている人に向けて現役理学療法士の体験談を紹介
公開日:2022.08.19 更新日:2023.03.14
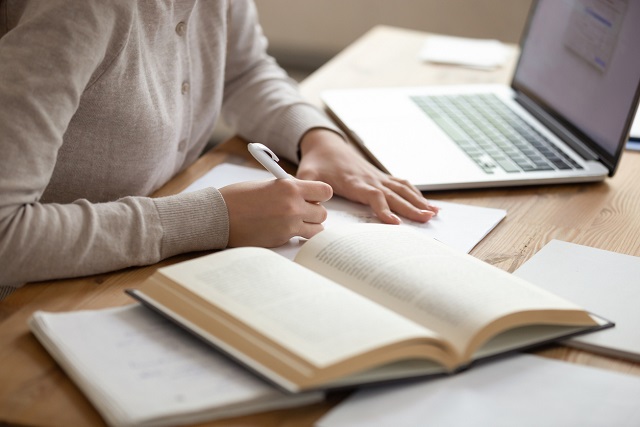
文:rana(理学療法士)
理学療法士の資格を取得するには、国家試験に合格する必要があります。そのため、多くのことを勉強しなければなりません。これから理学療法士を目指すうえで、養成校の勉強についていけるのか不安に思っている人も多いのではないでしょうか。今回は経験年数14年目の理学療法士が、理学療法士になるための勉強内容について解説していきます。
理学療法士養成校で学ぶ勉強内容
理学療法士養成校で学ぶ内容は、大きく分けて「基礎科目」「専門科目」「実習」「国家試験対策」の4つがあります。まずはそれぞれの概要について見てみましょう。
基礎科目
主に1年次に学ぶのが基礎科目で、作業療法士を目指す人とも共通する内容です。主なものについてまとめました。
【解剖学】
人体の構造を学びます。骨、筋肉、靭帯、関節、内臓、皮膚、筋膜といった組織についての知識を深めます。
【生理学】
諸器官の生理的な働き方について、筋肉が動く仕組み、エネルギーが産生される仕組み、反射が起こる仕組みなどを学びます。
【運動学】
動作の遂行に必要な運動力学について、歩行時に働く筋肉、床反力やモーメント、重心など臨床で応用する知識を身につけます。
【リハビリテーション概論】
リハビリテーションとは何かについて学びます。リハビリテーションの歴史、目的、医療施設や時期による違い、今後の在り方などの知識を深めます。
専門科目
2年次になると基礎科目で学んだ内容よりも、より理学療法士としての専門性が高い科目を学んでいきます。主な科目についてまとめました。
【理学療法評価学】
患者さんの状態を評価する具体的な方法を学びます。主な項目として、関節可動域測定、徒手筋力検査、反射検査、脳神経検査、バランス検査、バイタルサイン測定などが挙げられます。
【運動療法学】
臨床で行う運動療法の方法として、関節可動域訓練や筋力増強訓練、呼吸訓練、動作訓練などの具体的な方法を学びます。
【物理療法学】
温熱療法、電気療法など物理エネルギーを用いた治療法について学びます。
【整形外科学、神経内科学、内科学】
リハビリで遭遇しやすい、各専門診療科目における病態について学びます。
【義肢装具学】
義肢装具の種類、疾患ごとの適応、使用方法などについて学びます。
【地域理学療法】
訪問系、通所系、施設系といった地域理学療法の概要や役割について学びます。
実習
3年次、4年次になると実際の医療現場で、理学療法士の業務を経験する実習が行われます。実習は主に3つの種類に分けられます。
【見学実習】
主に先輩理学療法士が実施しているリハビリを見て学ぶ実習です。養成校によりますが、数日〜1週間程度の期間で実施されます。
【評価実習】
実際に患者さんの関節可動域や筋力などを測定し、評価結果から、統合と解釈をまとめるスキルを学ぶ実習です。2〜4週間程度の期間で実施されます。
【臨床実習】
臨床に出たことを想定して、患者さんの評価、治療までの一連の流れを実施するスキルを学ぶ実習です。8〜10週間程度の実習を2回行います。
国家試験対策
上記の学習を踏まえ、3年次または4年次の夏頃からは、国家試験の対策が始まります。苦手な分野の復習をしながら、過去問を解いて本番に備えます。
筆者の養成校体験談
筆者は昼間に仕事をしながら、夜間の養成校に4年間通った経緯があります。養成校の授業は決して楽ではありませんでしたが、しっかりと復習をして、日々の勉強を重ねていけばそこまで困難には感じませんでした。ただ、定期テスト前はしっかりと時間を確保し、集中して勉強をしなければ、良い点数を取るのは難しいです。テストでは暗記力が求められることが多いので、仕事の昼休みや通学の電車の中など、隙間時間も使いながら必死に暗記していたことを覚えています。
1番難関だったのは実習
理学療法士になるための勉強として、周りの人の多くは「1番大変なのは実習」と声を揃えて言います。筆者自身もそうでした。実習では、実際に患者さんのリハビリをするのですが、教科書通りにならないことが多く、臨機応変な対応をしなければなりません。
また、知識だけではなく、接遇や態度、コミュニケーション能力も必要となるため、テストで良い点を取れても、それだけでは上手くいかないことがほとんどです。期間も長く、忍耐力や継続力も求められるため、それなりの覚悟を持って臨む必要があります。
大変な勉強を経てこそ立派な理学療法士
患者さんに直接関わる理学療法士は、その人の今後を左右する責任ある仕事です。そのため、資格を取得するためにはそれなりの苦労が必要であることは念頭に置いておきましょう。勉強をするうえで大切なことは、資格を取るためではなく、将来的に患者さんを支援するために勉強するという認識を持つことです。臨床に出て、学んだことを患者さんに還元できるよう、頑張っていきましょう。
>>【全国どこでも電話・メール・WEB相談OK】セラピストの無料転職サポートに申し込む

rana(理学療法士)
総合病院やクリニックを中心に患者さんのリハビリに携わる。現在は整形外科に加え、訪問看護ステーションでも勤務。 腰痛や肩痛、歩行障害などを有する患者さんのリハビリに日々奮闘中。 業務をこなす傍らライターとしても活動し、健康、医療分野を中心に執筆実績多数。
他の記事も読む
- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説
- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介
- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説
- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説
- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?
- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説
- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介
- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説
- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説
- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説
- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説
- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説
- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説
- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説
- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!
- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説
- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説
- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介
- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説
- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説
















