燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?なりやすい人の共通点と対策
公開日:2021.05.11 更新日:2023.04.28
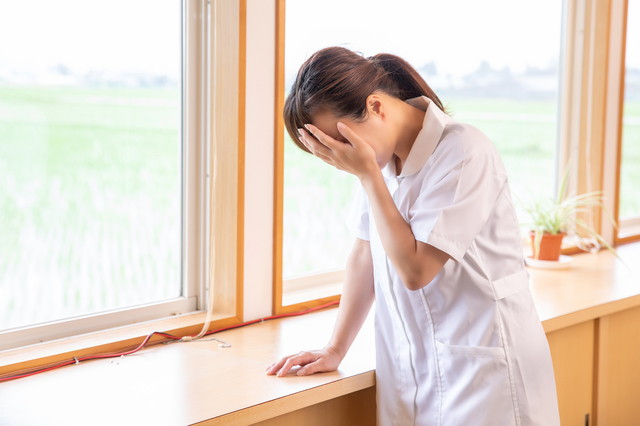
文:中山 奈保子
作業療法士(教育学修士)
意欲的に仕事に向き合う人であれば、誰もがそのリスクを抱える「燃え尽き症候群(バーンアウト)」。セラピスト、看護師、保育士など、他者への献身性が必要とされる対人援助職に従事する人は、特にそのリスクが高いとされています。
対人援助職のメンタルヘルスは、決して自己責任だけで守るべきものではありません。必要なときに助けを求め合える、「お互いさま」の気持ちをもって働ける職場環境づくりも大切な備えのひとつです。
■関連記事
セルフコントロールとは?自己管理能力を高める4つの方法
目次
「燃え尽き症候群」とは?医療従事者の間で起きやすい理由
「燃え尽き症候群(バーンアウト)」とは、それまで意欲をもってひとつのことに没頭していた人が、まるで燃え尽きて灰になってしまったかのように、身体と心のエネルギーが失われ、急に何もできなくなってしまう状態を指します。
当たり前のように送っていた生活のリズムが乱れはじめたり、いつも楽しみにしていた時間を急に楽しめなくなってしまったり、突然イライラしてしまったりするような変化は、そのサインであるかもしれません。
燃え尽き症候群は、絶え間ない過度のストレスにより発症すると言われており、医療や福祉、教員など対人援助職に従事する人に多いことが指摘されています。
フロイデンバーガーは、「持続的な職務上のストレスに起因する衰弱状態により、意欲喪失と情緒荒廃、疾病に対する抵抗力の低下、対人関係の親密さの減弱、人生に対する慢性的不満と悲観、職務上の能率低下と職務怠慢をもたらす症候群」と定義しています。
うつ病の一種と考えられており、「燃え尽き症候群」になるとうつ病に見られる以下のような症状があらわれることがあります。
燃え尽き症候群のおもな症状
- 朝、起きられなくなる
- 仕事に行きたくない
- アルコール量が増える
- イライラする
- 仕事が手につかない
- 対人関係を避ける
- 免疫力が低下して風邪などにかかりやすくなる
心身の不調により、人生にも悲観的になることから、最悪の場合、自殺や過労死に至ることもあります。
医療従事者として働く以上は、「燃え尽き症候群」についての知識をもち、自身のメンタル不調を見逃さず、きちんと対処することが必要だと言えます。
医療現場での「燃え尽き症候群」のあらわれ方

仕事中に「何もかも疲れ果ててしまった」と感じたり、熱心に取り組んできた仕事が急に嫌になってしまったり、ちょっとしたミスについ感情的になってしまったり…臨床に携わるセラピストなら、誰でもこのような経験をしたことがあるかもしれません。
単なる疲れで片付けてしまうと、「燃え尽き症候群」による心身のSOSを見落としてしまうかもしれません。なぜそのような心境になったのか、客観的に自己分析してみることも大切です。
患者さんのためにと仕事に没頭していた新人時代
私が臨床業務に就いていた頃を振り返りますと、大小問わずたくさんの“燃え尽き”体験を繰り返していたと思います。特に、新人の頃は頻繁に体験していました。
「患者さんの役に立ちたい」「患者さんが満足することがやりがいなのだ」という思いが強すぎたせいでしょうか。純粋に仕事に没頭していたために、自分の感情を客観的に捉えて、ちょっと患者さんと距離を置いたり、感情を調整したりする働きかけができていなかったのだと思います。
同時に、学生時代に思い描いていた臨床のイメージと現実のギャップに反発したり、「自分は本当に求められているのだろうか?」と悩んだりもしていました。
病院に行っても診断がつかない腹痛や喉の痛み、腰痛、足のむくみ、夜間の中途覚醒、無気力など、さまざまな不調に苦しめられました。燃え尽き症候群と診断されたわけではありませんが、当時の状態を思い返してみると、“燃え尽き”体験の繰り返しに原因があったと考えられます。
経験を重ね、がんばりすぎる自分にブレーキをかけられるようになり、何かあれば遠慮せず周囲に相談ができるようになってからは、だいぶ落ち着きましたが「これは、危険な状態だな」と、いまだに黄色信号を感じることがあります。
「燃え尽き症候群」はさまざまな場面であらわれる可能性がある
東日本大震災後の被災地でも、生活再建のために必死でがんばる被災者や、その支援活動に精力的に取り組む人たちの間で、「燃え尽き症候群」が見られました。
責任感が強く、自分の役割を精一杯果たそうと限界までがんばった結果、無力感や脱力感に襲われたり、思うように動けなくなったりする状態に陥ります。夢中で動かなくてはならない緊急期を抜け、ふと立ち止まったような時期に、「燃え尽き症候群」が起こりやすいようです。
私自身も、東日本大震災後の避難生活で同様の体験をしました。
仮設住宅での生活がはじまり、日常が失われた日のことを忘れられない一方で、生活再建に向けてポジティブな気持ちに満たされてもいました。そのような複雑なメンタル状態のなかで、仮設住宅で行われる集会の取りまとめ役を任されたり、自分から進んで引き受けたりしていたのです。
「私も、被災地の復興に少しでも役立ちたい」
こんな思いが高まり、夢中になって新たに与えられた役割に徹した結果、体調を崩して家事を放棄してしまうこともしばしば。そんな自分に罪悪感を抱き、もう、部屋の外に出たくない、人に会うのも嫌…と思ってしまうことも。いま思えばこれも、「燃え尽き症候群」の一種だったと考えられます。
そんな私を支えてくれたのは、「ちょっと休んでもいいから、またお願いね」「あなたの健康が第一だから、今は休んで欲しい」と休養の機会を与えてくれた家族や仲間だったと思います。
休養の時間は、とにかく睡眠と栄養をとることに努め、起きている時間はひたすら好きな映画を観ていました。そうしているうちに自然とエネルギーが回復し、「あ、そろそろこうしちゃいられないぞ」と思うことができました。
「燃え尽き症候群」は、仕事以外でも起こりうる症状です。
進行すると重度のうつ状態になることもあるため、ひとつのことに没頭しているときほど注意が必要です。自分の役割を果たそうとがんばっているときには、自覚していなくてもストレスを感じていることを意識しましょう。
対人援助職のメンタルヘルスは「自分を守る」「みんなを守る」

セラピストとして働くなかで、「燃え尽き症候群」を防ぐためには、自分自身のストレスケアがとても重要です。日ごろから次のようなことを心がけてみてください。
- セラピストのための「燃え尽き症候群(バーンアウト)」予防対策
- (1) 自分も「燃え尽き症候群(バーンアウト)」になるかもしれない可能性を常に意識する
(2) ストレスの原因を見極め、適度に距離を置く時期をつくって、体調を整える
(3) 自分のストレスを軽減するために、気持ちを開放できる方法を見つけておく
新人の頃、「対人援助職のメンタルヘルスは、自己責任だよ」と、先輩に教わったことを今でもよく覚えています。
やはり、身体的にも精神的にも疲れがたまっているときや、ストレスにさらされ続けているときこそ調子を崩しますから、食事と睡眠のバランスを図り、適度な運動と、余暇時間の充実に努めることは、対人援助職の責務と言えるでしょう。
しかし、対人援助職のメンタルヘルスは、一人だけで抱えられる問題ではありません。ストレスの原因がわかっていても、患者さんが相手では距離を置くことも簡単ではありませんし、休みを取るにも周囲の協力が必要です。
そのため、「燃え尽き症候群」予防のためのサポート体制として、その困ったときに声を掛け合える、手を取り合える環境づくりは欠かせません。一人一人が「助けを求めるスキル」「自分を客観的にみつめて感情を調整するスキル」を伸ばすことも求められます。
また、管理職になれば、スタッフがやりがいをもって仕事に就けているかどうか、達成感や自己肯定感が得られやすい環境になっているかどうか見守る意識も、「燃え尽き症候群」予防のために必要だと考えます。
■関連記事
478呼吸法とは?心と身体をリラックスさせる4つの手順と注意点

中山 奈保子(なかやま なおこ)
作業療法士(教育学修士)。
1998年作業療法士免許取得後、宮城・福島県内の医療施設(主に身体障害・老年期障害)に勤務。
現職は作業療法士養成校専任教員。2011年東日本大震災で被災したことを期に、災害を乗り越える親子の暮らしを記録・発信する団体「三陸こざかなネット」を発足し、被災後の日常や幼くして被災した子どもによる「災害の伝承」をテーマに執筆・講演活動を行っている。
他の記事も読む
- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説
- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介
- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説
- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説
- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?
- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説
- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介
- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説
- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説
- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説
- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説
- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説
- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説
- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説
- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!
- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説
- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説
- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介
- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説
- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説
















