インナーマッスルはどんな筋肉?主な働きやトレーニングのメリットを解説
公開日:2024.06.19

文:内藤 かいせい(理学療法士)
「インナーマッスル」という言葉を聞くものの、どんな筋肉なのかいまいちわからない方もいるのではないでしょうか。インナーマッスルとは、身体の深層にある筋肉のことで、関節の安定性を高める役割があります。
この記事では、インナーマッスルを鍛えることで得られる効果や、おすすめのトレーニングメニューについてご紹介します。筋肉についての理解を深めることで、効果的な筋トレを実践できるようになるでしょう。
目次
インナーマッスルとは?
インナーマッスルとは、身体の深い部分についている筋肉のことです。インナーマッスルは関節の安定性を高める働きをしており、身体のバランスを保つためには欠かせない筋肉です。インナーマッスルは体幹についている筋肉というイメージを持っている方もいると思いますが、肩関節や股関節にも存在しています。
それぞれについている代表的なインナーマッスルは、以下のとおりです。
● 腹横筋(ふくおうきん):腹筋の奥についている筋肉
● 多裂筋(たれつきん):腰の奥についている筋肉
● 横隔膜:胸郭の下についている筋肉
● 骨盤底筋群:骨盤の下についている筋肉
● 肩甲下筋
● 棘上筋(きょくじょうきん)
● 棘下筋(きょくかきん)
● 小円筋
それぞれ肩関節のまわりについており、4つをあわせて「ローテーターカフ」と呼びます。
● 深層外旋六筋:股関節につく6つの小さい筋肉の総称
● 腸腰筋(ちょうようきん):股関節の前面についている筋肉
インナーマッスルとアウターマッスルの関係性

筋肉は大きく「インナーマッスル」と、「アウターマッスル」の2種類に分けられます。アウターマッスルとは、身体の表面部についている筋肉のことで、関節を動かす役割があります。
代表的なアウターマッスルは、以下のような大きな筋肉です。
● 大胸筋:胸の筋肉
● 上腕二頭筋:上腕の力こぶができる筋肉
● 大腿四頭筋:太ももの筋肉
● 下腿三頭筋:ふくらはぎの筋肉
アウターマッスルとインナーマッスルは、それぞれ協調的に働くことで、身体の安定性を高めながら関節を動かせます。反対に、両方の筋肉がうまく連携できていないと、身体をスムーズに動かしにくくなります。身体を動かすためには、アウターマッスルとインナーマッスルの両方の働きが欠かせないのです。
インナーマッスルを鍛えることで得られる効果

インナーマッスルを鍛えることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここではインナーマッスルを鍛える効果について詳しく解説します。
体幹や関節が安定しやすくなる
インナーマッスルを鍛えることで、体幹や関節の動きが安定しやすくなります。体幹や関節の動きが安定するようになれば、運動のパフォーマンスの向上、転倒予防などにつながります。
たとえば、肩関節のインナーマッスルを鍛えれば、野球やバレーなどの肩を動かすスポーツのパフォーマンス向上につながるでしょう。また、股関節や体幹部のインナーマッスルを鍛えれば、姿勢が改善されて腰痛や肩こりなどの身体の不調予防にもなります。
痩せやすい身体を作れる
インナーマッスルを鍛えることで、基礎代謝が高まって痩せやすい身体を作れます。基礎代謝とは、人が生きるのに必要な最低限のエネルギーのことです。基礎代謝を決める要素には筋肉量や臓器の働きが関わっています。そのため、インナーマッスルを鍛えることで基礎代謝量の向上が期待できます。
基礎代謝量が上がれば消費エネルギーが増加し、普段よりも痩せやすくなるのです。アウターマッスルと一緒に鍛えることで、さらに基礎代謝量を上げられるでしょう。
インナーマッスルを鍛えるトレーニングメニュー
ここでは、インナーマッスルを鍛えるおすすめのトレーニングメニューをご紹介します。器具を使用せずにすぐできるので、ぜひ気軽に試してみましょう。
ドローイン
ドローインは腹式呼吸で体幹のインナーマッスルを鍛えるトレーニングです。関節を動かさないトレーニングなので、腰痛の方でも気軽に行えます。
1. あお向けになって両膝を立てる
2. 息を吸った後、お腹をへこませながら口でゆっくり吐く
3. 息を吐き切ったら、再び2の手順を行う
4. 2〜3の手順を2〜3セット行う
ドローインが上手に行えない場合は、腰の下にタオルを敷くのもおすすめです。息を吐く際にタオルを下に押し付けるイメージで行うと、体幹のインナーマッスルに効かせやすくなります。
プランク
プランクは、体幹のインナーマッスルを鍛えるトレーニングです。
1. うつ伏せになり、両肘と腕を床につける
2. 身体を浮かせて、上半身と下半身を一直線にした状態をキープする
3. 20〜30秒ほどキープしたらゆっくりと元に戻る
4. 2〜3の手順を2〜3セット繰り返す
プランク中は身体を曲げないように、まっすぐの状態を意識しましょう。また、呼吸を止めないように注意してください。
プランク【シングルハンド・レッグキープ】
通常のプランクよりも難易度が高いトレーニングです。プランクの状態で片手または片足を伸ばして行うので、肩関節や股関節のインナーマッスルも効きやすくなります。
1. うつ伏せになり、両肘と腕を床につける
2. 身体を浮かせて、上半身と下半身を一直線にする
3. 片手または片足を上げた状態をキープする
4. 10〜20秒ほどキープしたらゆっくりと元に戻る
5. 2〜4の手順をそれぞれの手足で行う
手を上げる際は、上半身を大きくひねらないように注意してください。
バードドッグ
バードドッグは、四つ這いの状態から左右の手足を上げるトレーニングです。体幹や各関節のインナーマッスルを鍛えることが可能です。
1. 四つ這いになる
2. 体幹と一直線になるように右手と左足を上げる
3. 上げた状態を10〜20秒キープしたらゆっくりと元に戻る
4. 反対の手足で2〜3の手順を行い、左右で2〜3セット繰り返す
トレーニング中は腰を反らせすぎたり、丸くしすぎたりしないように注意してください。顔はなるべく前に向けながら行ってみましょう。
インナーマッスルを鍛える際のポイント
インナーマッスルを鍛える際は、どのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。ここでは、効率的に鍛えるときのポイントを解説します。
負荷をかけすぎない
インナーマッスルを鍛えるときは、負荷をかけすぎないようにしましょう。基本的にトレーニングは、負荷が強ければその分筋肉が働きやすくなります。しかし、インナーマッスルにはその法則が当てはまりません。負荷が強すぎると、インナーマッスルではなくアウターマッスルが優位に働きやすくなるからです。
トレーニングの際は負荷の低い運動をゆっくり、反復的に行うことが大切です。先ほど紹介したインナーマッスルのトレーニングも、なるべく力を入れすぎないように注意して行いましょう。
呼吸を意識しながら行う
トレーニング中は、呼吸を意識しながら行いましょう。体幹のインナーマッスルには、関節を安定化させるだけでなく、呼吸をサポートするものも多く存在しています。呼吸を意識して行うことで、より効率的にインナーマッスルを鍛えられるでしょう。
また、呼吸を止めてしまうと血圧が上昇しやすくなるので、身体にも負担がかかってしまいます。
適切な方法でインナーマッスルを鍛えよう
インナーマッスルは身体の深い部分についている筋肉で、関節を安定させる働きがあります。身体を安定させながら関節を動かすためには、アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルの活動が必要不可欠です。また、インナーマッスルを効率的に鍛えるためには、強い負荷をかけすぎず、呼吸を意識して行うことが大切です。インナーマッスルの仕組みを知り、適切な方法でトレーニングを実践していきましょう。
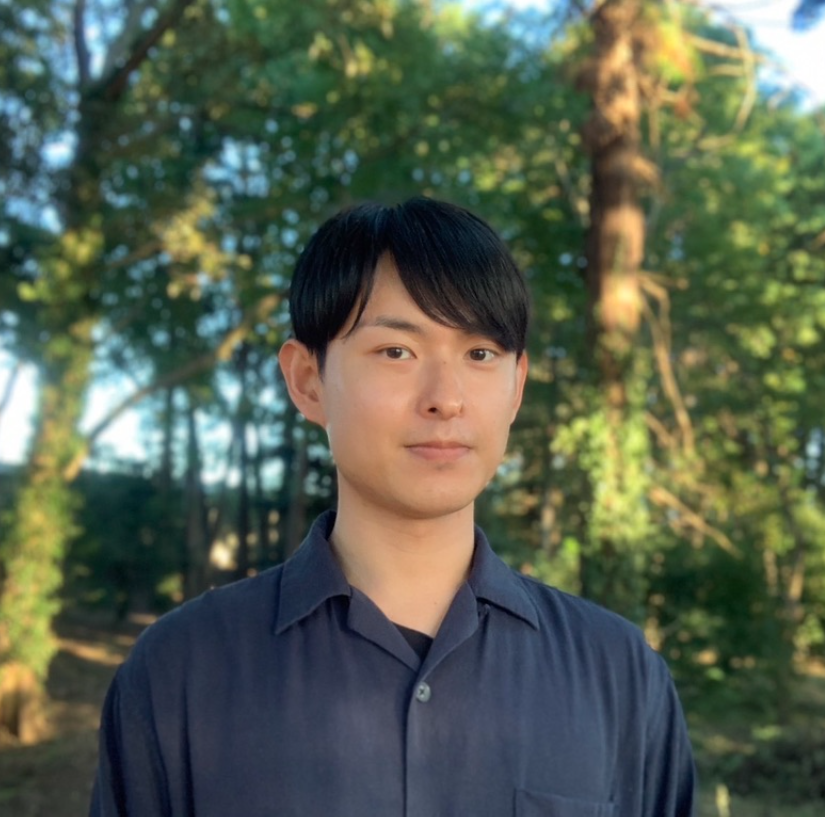
内藤 かいせい
理学療法士として回復期病院と訪問看護サービスに従事し、脳血管疾患や運動器疾患などの幅広い症例を経験する。リハビリで患者をサポートするとともに、全国規模の学会発表にも参加。 新しい業界にチャレンジしたいと決意し、2021年に独立する。現在はWebライターとして活動中。これまでの理学療法士の経験を活かして、医療や健康分野で多くの執筆・監修に携わっている。
他の記事も読む
- シーテッドローのやり方は?どこに効くの?効果やポイントを解説!
- ショルダープレスの効果的なやり方は?鍛えられる部位や重量について解説
- アームカールで引き締まったたくましい腕を手に入れる!正しい方法や注意点を解説!
- プロテインはいつ飲むのがベスト?おすすめのタイミングと効果を出しやすくする方法を徹底解説
- 毎日の筋トレは逆効果は嘘?正しい頻度と即実践できる効果的な方法を徹底解説!
- 筋トレに最適なインターバルは?自分に合った時間を考える方法を解説
- 筋トレはメリットだらけ?その効果とデメリットの解決法もあわせて解説
- フロントレイズの効果的なやり方とは?重量やポイントについて徹底解説
- リバースプッシュアップはどこに効く?正しいやり方や効果を解説
- 懸垂ができない原因と対策を徹底解説!すごい効果を引き出す正しいやり方とは?
- コンセントレーションカールの正しいやり方は?効果や注意点もあわせて解説!
- サイドレイズのやり方は?重量目安や正しいフォームを解説!
- バックエクステンションの正しいやり方は?効果や注意点も合わせて解説!
- ペックフライの正しいやり方は?重量目安や効果について解説!
- 短期間で理想の胸筋を目指す!インクラインベンチプレスの効果的なトレーニング方法
- レッグレイズの正しいやり方・効果について徹底解説!
- ウォーキングの効果を高める方法とは?効果が出るまでどのくらいかかるか解説!
- 【ピリピリ痛む】坐骨神経痛の原因と症状別ストレッチについて解説!
- 【膝がポキポキ鳴るのはなぜ?】膝音の原因と対処ストレッチを徹底解説!
- 【四十肩・五十肩の方にオススメ】根本から解決したい肩関節周囲炎ストレッチを解説!





















