手指のリハビリが必要なのはこんなとき!自宅でできる自主トレ方法も紹介
公開日:2024.02.03 更新日:2024.02.19

文:伊東浩樹(理学療法士)
手指を使って握る、ひねる、つまむなど、手指を使う機会は多く、日常生活に欠かせない大切な機能です。
しかし、骨折や脳卒中、その他の原因によって手指に痛みが出たり、ある一定の角度から関節が動かなくなってしまったりするなど、気になる症状があるときには、自主トレも含めたリハビリを行うことが大切です。
今回は、現役理学療法士が、自宅でできる手指のリハビリとして自主トレ方法を紹介します。
手指のリハビリが必要になる疾患
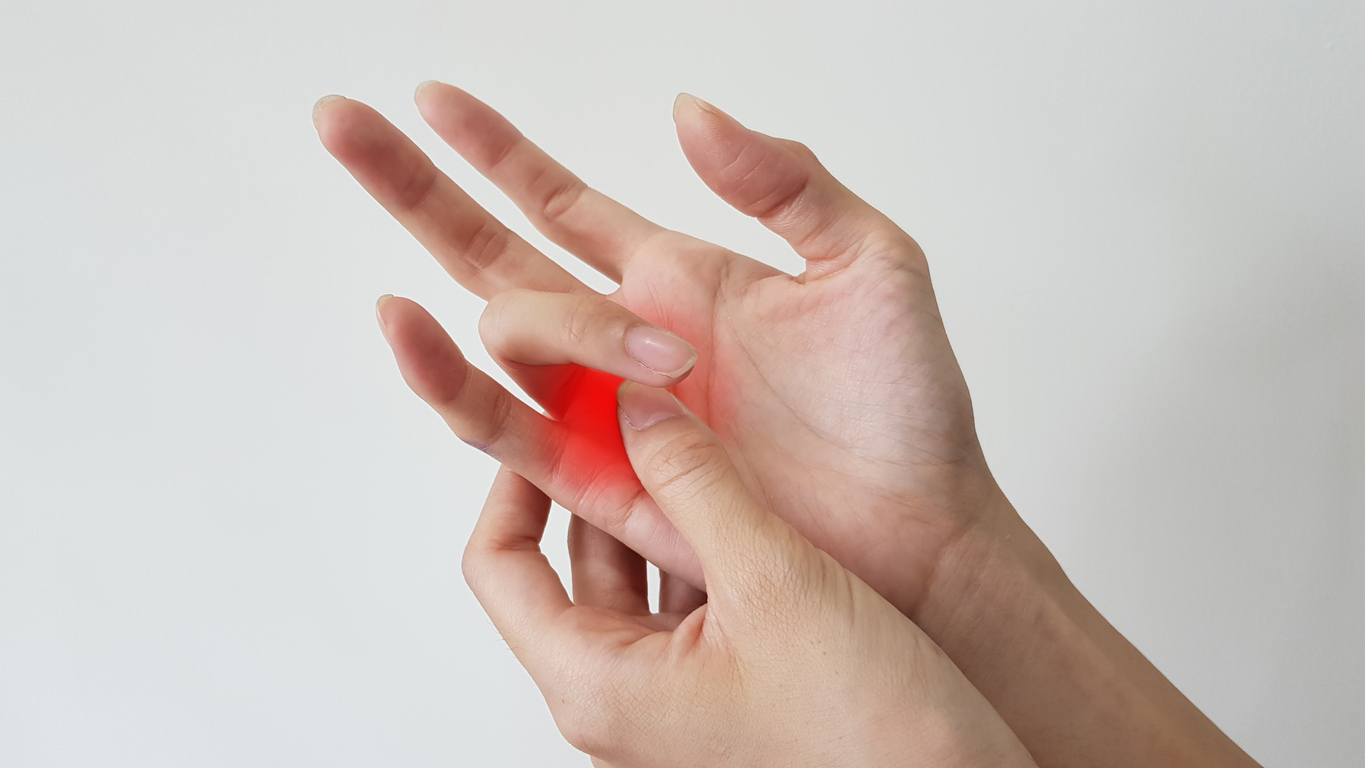
手指のリハビリが必要とされるのは、痺れや痛みが生じているときや、関節が動かしにくいときなどさまざまです。いずれの場合でも、リハビリが必要かどうかは自己判断せず、整形外科といった医療機関を受診し、疾患名を特定してもらうことが大切です。
自己判断でリハビリを行うことで症状が悪化してしまう可能性もあるため、医療機関で適切なリハビリや対処法などの指示・指導を受けてから自宅で実施するようにしましょう。まずは、手指に症状が出現しやすい疾患について解説します。
腱鞘炎、ばね指
指を酷使することで、手首や指を動かした際に痛みが生じる場合は腱鞘炎(けんしょうえん)の可能性が高いでしょう。腱鞘炎の場合は、指や手首を動かす腱が通る「腱鞘(けんしょう)」というトンネルが、炎症を起こして痛みが生じます。保存療法による治療のほか、狭くなった腱鞘を開く手術療法を選択する場合もあります。
パソコン作業など、指を使う仕事を日常的に行う職業の人に多く見られますが、最近ではスマートフォン操作の影響で発症する人も増えています。
また、痛みが生じるだけでなく、指を曲げる際に一瞬引っかかったように感じ、指を伸ばすときに勢いよく伸びる「ばね指」も腱鞘炎の一種です。
へバーテン結節
指に生じる変形性関節症をヘバーデン結節といいます。
指の第一関節にある軟骨がすり減って、関節が変形し、腫れが生じます。痛みがあり、水イボのような膨らみができることもあります。
手をよく使う人に起こりやすい傾向にありますが、関節症状をきたすものであり、リウマチとの判別も大切です。
骨折
指の骨折時は固定期間があるため、関節が動かしづらくなり、固まってしまう拘縮(こうしゅく)という状態になることがあります。
その際には関節を動かすリハビリが大切ですが、痛みを生じるおそれがあるため、動作は慎重に行う必要があります。
関節リウマチ
30代から40代の女性に多く発症するといわれる関節リウマチ。初期症状としては、朝の強張り、手首や指などの関節の痛みと腫れ、熱感です。
また、手指のみではなく、足やその他の関節にも症状が出ることがあり、指の第二関節に症状が出やすいとされております。
第一関節に症状が出やすいへバーテン結節と判別が重要です。また、自己免疫疾患のため倦怠感や微熱などの全身症状が出現することもあります。
■関連記事
関節リウマチでやってはいけない仕事とは?向いている仕事や働きやすい職場環境について解説
頚椎症
手指そのものから痛みを生じている場合もあれば、首の整形疾患によって手指に痺れと疼痛が起きることもあります。
多くの場合は、頚椎症(けいついしょう)からくる症状ですが、顔を上に向けた状態で、首を左右に倒したときに同じ方向の手指に痺れが生じた際には、首からの症状を疑った方がよいかもしれません。
脳卒中
整形外科疾患とは別に、脳の疾患によっても手指に異変を生じることがあります。
脳卒中の影響で、片方の指に痺れや、指が動かしにくい、力が入りにくいといった症状が出る場合には、リハビリが必要です。
その他
そのほか、糖尿病の症状として、手指に痺れが現れることがあります。
ただし、糖尿病の場合、手指に症状が現れるのは末梢神経症状であり、糖尿病が進行した状態です。
特に左右の手に痺れがある際には危険なサインと考えた方がよいでしょう。こうした糖尿病由来の手指の痺れにも、リハビリが有効なケースがあります。
自宅でできる手指の自主トレ・リハビリ方法

疾患名がはっきりした後は、保存療法か手術療法のいずれかを選択して治療することになるでしょう。
治療中、日常生活に支障が出る際には病院でのリハビリが行われますが、無理のない範囲で自宅での自主トレも取り入れてみてはいかがでしょうか。
大前提として痛みが起きない範囲で実施することが大切です。主な方法を紹介します。
筋力トレーニング
自宅で行う手指のトレーニングとして、手軽に実施しやすいのが筋力トレーニングです。
手を広げたり閉じたりするグーパー運動を行うだけでも効果があります。また、柔らかいボールなどを用意し、握ったり緩めたりして握力を強化し、指全体の筋力を鍛えてみましょう。
関節運動
関節運動を実施する際は、痛みがないことを確認したうえで、両手を使って片方の手指を伸ばしたり、曲げたりします。
右手のトレーニングをする際は、左手で右手をつかんで、曲げ伸ばしを手伝ってあげるとよいでしょう。麻痺やリウマチ、拘縮などの症状により、自分で手指の関節を動かすことが難しい場合は、家族に協力してもらうのがおすすめです。
その際、痛みや痺れなどが生じる場合は、無理して実施する必要はありません。ゆっくりと痛みのない範囲で動かすようにしてください。日常生活で必要な動きができる程度に、関節の可動域を広げることを目的とした自主トレです。
温熱療法
拘縮などで、指の筋肉や関節が固まってしまっている際には、痛みがなければ温熱療法を取り入れるのもよいでしょう。
筋や周辺組織を温めて、柔らかくすることで、動きにくかった手指が動かしやすくなります。病院等でのリハビリでは、機械を使うケースもありますが、自宅では、熱すぎない温度のお湯を、お風呂や洗面器などに用意し、15分ほどつけて様子をみましょう。
片方ずつお湯につけながら、反対の手でマッサージをするとよりよいでしょう。
■関連記事
拘縮とは?概要や原因、予防方法などについて解説
手指のリハビリは、無理のない範囲で行おう
手指の痛みや動きにくさは、手指を多く使う仕事をしている人だけでなく、加齢によって起こることもあります。
普段からよく動かすように意識することが大切ですが、場合によっては疾患によって手指に異変が起きていることも考えられます。いつもと様子が違うと感じたときには、自己判断せずに、病院を受診することが大切です。
症状などによっても異なりますが、医師や理学療法士などの専門家に相談しながら、自主トレも取り入れて、回復を目指しましょう。
■関連記事
作業療法士が治療で「折り紙」を用いる目的とは
>>【全国どこでも電話・メール・WEB相談OK】セラピストの無料転職サポートに申し込む

伊東 浩樹(理学療法士)
学療法士として総合病院で経験を積んだ後、予防医療の知識等を広めていくためにNPO法人を設立。その後、社会福祉法人にて障がい部門の責任者や特別養護ホームの施設長として勤務。医療機関の設立や行政から依頼を受けての講演、大学、専門学校等での講師なども勤める。
他の記事も読む
- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説
- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介
- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説
- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説
- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?
- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説
- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介
- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説
- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説
- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説
- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説
- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説
- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説
- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説
- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!
- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説
- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説
- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介
- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説
- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説
















