人間力とは?日常でも意識できる「人間力を高める3つの方法」
公開日:2021.09.14

文:大久保 ゆうこ
(公認心理師/臨床心理士/精神保健福祉士)
例えどのような困難があろうと、その人らしい人生を送ってもらいたい。
誰かを支援するときに、このような想いで関わるセラピストや医療従事者は多いのではないでしょうか。ならば対人援助職こそ、自分らしい生き方ができる人間力が必要です。
人間力を身につける際の1つのヒントとして考えたいのが、「交流分析」で目指す自律性です。今回は心理士をはじめ、ビジネスや看護、教育現場などで広く活用される交流分析の哲学をベースに対人援助職に求められる「人間力」について解説します。
目次
人間力とは?ありのままの自分で力を発揮するために必要なちから
参考:今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について2(文部科学省)
つまり周囲の人と上手につきあいながら、自分の力を活かしていくための力といえます。単に他者との関係を円滑にするだけでなく、自分がどうあるべきかを考え、示していくために必要なものだともいえるでしょう。
交流分析が目指す「自律性」を考える
被援助者の多くは障害などの困難を抱えています。必死で生きる人たちに対して、うわべのお世辞は通用しません。その人がどのような状況であっても希望を持って、その人らしく生きていくことを願うなら、対人援助職は被援助者に対して希望を持ち、信じ続けるだけの人間力が必要です。
人間力を養ううえで、1つの参考になるのが「交流分析(TA)」の「自律性」です。交流分析(TA)は臨床心理学の一分野で「自律性の獲得」を目標としています。
「自律性」を簡単な言葉でいうと「自分らしく生きる」ことを指します。本音で関わることが大切な分野だからこそ、援助者こそ、ありのままの自分で力を発揮するための人間力が必要なのです。
人間力を高める「自律性」に基づいた3つの哲学
交流分析(TA)が目指す自律性「自分らしく生きること」を考えるうえで、覚えておきたいのが以下の3つの哲学です。
1.人は誰でもOKな存在である
例え犯罪者であろうと、存在として、誰もが肯定されるという考え方です。決して行動を全肯定するわけではありません。
被援助者のなかにはいろいろな性格の人がいます。被援助者に対して、腹が立つこともあるでしょう。時には、イライラした態度や言葉を出してしまい、そんな自分にがっかりするかもしれません。
交流分析(TA)ではそうした失敗や間違いを認め、そのままでOKとしています。被援助者がどのような態度をとっても、何をしても存在を肯定し、援助の突破口につながる可能性をつくります。
2.人は誰もが考える力を持つ
例えどのような障害があろうと、その人なりの考える力があり、責任を持っていると考えます。被援助者の持っている力や責任感から「できないから助けてあげよう」という発想になることがあるかもしれません。しかし、そうした考え方では、リハビリもうまくいかないでしょう。
お互いが能力を持ち、責任を持っているという前提に立つからこそ、力を出し合って効果を上げることができます。良い結果を目指すためにも、まずは自分自身が自分の力を信じることから始めましょう。
また、どこまでが自分の責任で、どこまでが相手の責任か、境界線を引くことも大切です。お互いの領分がわかって関わるときに、お互いの力が相乗効果となって力を発揮します。
3.人は自分の運命を決め、そしてその決定は変えることができる
どれだけ言葉を尽くしても、「私、こういう性格だから」といってあきらめる被援助者もいます。なかには、対人援助職でも同じように考える人がいるかもしれません。交流分析(TA)では、どのような性格でも関係なく、なりたい自分になることができるとしています。性格とは、自分が生まれ育ったなかで身につけたものです。
しかし見方を変えれば、自分で人生を選択したということ。ならば、これから考え方を自分で変えることも可能なはずです。そのままでいたければ、それでもOK。
逆に、変えたいなら変えられるということを知っておくことが大切です。人生は選択の連続。新たな選択をしていくことで運命は変えられます。
人間力を高めるには?日常で取り入れられる3つのポイント

上記の3つの哲学を踏まえ、日常のなかで取り入れられることを考えてみましょう。
すべてOKで考えてみる
迷ったときや、どうすればよいのかわからなくなったとき、まずは「みんなにとってOKなやり方はないか」と考えてみましょう。
「私はいいから」、「職員は我慢すべき」という考え方では、どこかでバランスを崩します。対人援助職が苦悶の表情を浮かべているのに、被援助者だけがリラックスして笑顔になるとは考えにくいものです。
作り笑顔も限界があります。自分も職場も大切にしてこそ、被援助者を大切にできると考えましょう。
ほしいものに「ほしい」という
「本当は助けてほしい、優しくしてほしい……だけどいえない」ということはありませんか?
「察して」では相手に伝わりません。ほしいものをほしい、やりたいことはやりたいという勇気を持ちましょう。
「~べき」よりも「~したい」を採用する
人間の仕組みとして、「頑張るべき」と思っても「怠けたい」という気持ちが勝つようになっています。
頭で「やらなきゃ」と思っても頑張れるのは一時的。人間は本音が一番強いのです。リハビリも「~べき」に立って行うと、良い結果は望めません。
やりたくない気持ちがあるならば、やりたくない気持ちに耳を傾けましょう。その先に突破口が開かれます。
対人援助職だからこそ、自分を大切にすること

対人援助職に必要な人間力とは、自分が自分らしくいられることであり、自分の人生を積極的に生きる力といえます。
具体的に見てみると「これは難しい」と思うこともあるかもしれません。それでもあきらめなければ次があります。大丈夫、あなたにも力はあります。自分らしく、ありのままでいて、自分の力を出せる存在として歩いていきましょう。
関連記事
セルフコントロールとは?自己管理能力を高める4つの方法
燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?なりやすい人の共通点と対策
>>【全国どこでも電話・メール・WEB相談OK】セラピストの無料転職サポートに申し込む
参考書籍
『TA TODAY―最新・交流分析入門』
著:イアン スチュアート、ヴァン ジョインズ/翻訳:深沢 道子(実務教育出版)
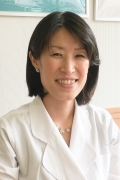
大久保 ゆうこ
臨床心理士/公認心理師/精神保健福祉士
精神科病院にて高齢者認知症病棟の担当心理士として活躍。現在は心療内科や電話相談などでカウンセラーとして多くの人の相談に応じている。著書に『食べる順番健康法-好きなものはがまんしないでいい』がある。
他の記事も読む
- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説
- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介
- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説
- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説
- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?
- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説
- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介
- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説
- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説
- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説
- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説
- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説
- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説
- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説
- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!
- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説
- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説
- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介
- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説
- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説
















