ひらがなが覚えられない・教科書が読めない―発達性読み書き障害とは?
公開日:2018.03.19 更新日:2018.04.04
学習障害(LD)のひとつ、発達性ディスレクシア(発達性読み書き障害)
言語聴覚士編の国試過去問ドリルでは、前回の高齢者のコミュニケーションに続いてお子さんの問題を取り上げます。「国試過去問ドリル」の第5回で発達障害の定義と分類を説明していますが、今回はその中の学習障害(LD)のひとつ、発達性ディスレクシア(発達性読み書き障害)についてお話します。
俳優のトム・クルーズやキアヌ・リーブス、映画監督のスティーヴン・スピルバーグ、作家ジョン・アーヴィングなど誰もが知っている有名人ですが、発達性読み書き障害であることでも知られています。典型的な読み書き障害のお子さんは、音声言語は正常で行動には問題がなく、知的にも遅れがないため周囲に気づかれにくいことも多い障害です。出現頻度は、調査にもよりますが英語圏の10~15%よりは低いものの、日本においても1クラスに数名の割合で存在する、ともいわれています。発達性読み書き障害の特徴や障害構造について詳しく解説することはここでは控えますが、国家試験の問題を解くときのポイントとして、「知的には問題がなく音韻処理と視覚情報処理に問題がある」ことを押さえましょう。
過去問題【言語聴覚士】
第8回 午後144
漢字の読み書きが覚えにくい(dyslexia)子どもの指導として、優先順位が低いのはどれか。
- 1. 漢字を繰りかえし模写させる。
- 2. 漢字の読みを復唱させながら書かせる。
- 3. 漢字の偏とつくりに分けてパズル形式で漢字を構成させる。
- 4. 漢字の書き順にそって「縦・横」など手の動きをことばにして書かせる。
- 5. 漢字の構成要素の意味を手がかりに覚えさせる。
解答
正解:1
■解説
選択肢にはありませんが、発達性読み書き障害のお子さんには「知的には問題がない」ため、知能検査を行い、学力に問題がないことを確認することが前提です。その上で、「視覚情報処理に問題がある」と考えてみると、発達性読み書き障害のお子さんに視覚認知機能や視覚性記憶を要する方法で読み書きの指導をすることが有効ではないことがわかります。視覚的な入力での指導は困難ですが、知的には保たれているため、聴覚的な入力で代償することが上手なことがあります。例えば、“親”という漢字を覚えるとき、通常であればノートに何度も“親”と書いて覚えますが、発達性読み書き障害のお子さんは書くのが遅い上に、他のお子さんと比べると字が下手。その上、何度書いてもなかなか覚えることができません。字が汚いと怒られ、書くのが遅いと怒られ、覚えられないと怒られ、それでは文字を書くことがどんどん嫌いになってしまいます。そこで「木の上に立って見ているのが親」と文字の形態を言語化して覚え、言いながら書くことで習得することが容易になります。
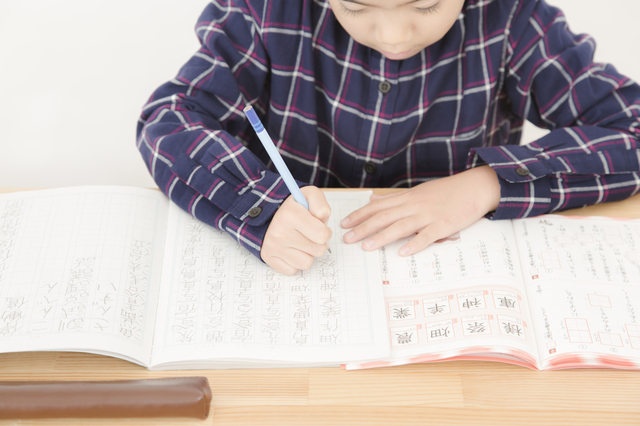
「音韻処理に問題がある」ために生じるのは、文章が上手にすらすら読めない、内容を理解しながら読めない、といった問題です。全く読めないわけではありませんが、読み方がたどたどしかったり読み飛ばしがあったり、文末などを適当に自分で変えて読んでしまったりなど、文字に関わる学習が苦手です。
このようなお子さんは、教科書を何度も読んで学習させることは有効ではありません。簡単な単語の音読を繰り返し行い速く読む練習をする、読み聞かせをすることで語の意味を理解する力をつける、などの工夫が必要です。また諸方法として、次のような方法が有効だと考えられます。例えば、トム・クルーズは台本の文章が読めないため、アシスタントに読んでもらいそれを聞いてセリフを暗記する方法をとっているそうです。他にも、以下の方法が有効と考えられます。
- ● 文字を大きくしフォントを変える
- ● 文節(文章の区切り)ごとに「/」を入れる
- ● 重要な単語に蛍光ペンで色をつける
- ● 行間を広くする
- ● 読む行以外を隠す
また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、学校生活において「子どもの特性に合わせた合理的配慮を可能な限り提供すること」が求められるようになりました。読み書きが困難なお子さんに対しては、文字を見やすくした教科書やタブレットの使用、音声読み上げソフトの利用、試験時間を延長したり漢字にふりがなを振る、などの配慮により、力を発揮できることが期待できます。
まとめ
発達性読み書き障害の認知度は低く、一般的な理解のみならず、教育現場やコミュニケーション障害の専門家である言語聴覚士でも、充分に対応できているとは言えない状態です。
読み書きが苦手なことで知識の幅が狭まるだけでなく、本人は頑張っているのに周りから“怠けているからできない”と思われ、叱られることで自信をなくし自分は頭が悪いのだと思ってしまったり、うつ病や不登校といった2次障害となってしまう可能性もあります。専門職として正しい知識と支援方法を学びましょう。

新家 尚子
東京都言語聴覚士会 理事 保険局局長
大学を卒業後一般の企業で5年間社会人を経験した後専門学校に入学し、卒業後は急性期、回復期病院への勤務を経て、現在は訪問看護ステーションに勤務。
 東京都言語聴覚士会
東京都言語聴覚士会
東京都におけるすべての言語聴覚士が本会に入会され、自己研鑽に励み、地域社会に貢献することを目指し、活動中。
活動内容や入会のお問い合わせはこちらから。
http://st-toshikai.org/
他の記事も読む
- 生活期における言語聴覚療法
- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント
- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法
- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導
- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について
- 赤ちゃんの座位発達段階について
- 糖尿病患者に対する適切な運動療法
- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション
- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?
- 二分脊椎と脊髄係留症候群について
- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応
- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい
- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入
- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法
- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション
- 大人の発達障害と作業療法
- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入
- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション
- 高次脳機能障害の作業療法
















