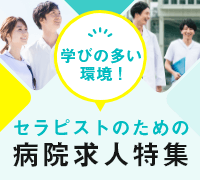【言語聴覚士が解説】自宅でできる構音障害のリハビリ方法7選!
公開日:2024.10.07

文:tokoshi(言語聴覚士)
構音障害(こうおんしょうがい)とは、唇や舌、声帯などの「声を出すための器官」に何らかの問題があり、うまく発声や発語ができない状態を指します。
構音障害がある場合、コミュニケーション面で支障をきたすだけでなく「飲み込み」に問題が出てくるケースも。構音障害は適切なリハビリをすることが改善の近道です。本記事では、現役言語聴覚士が、構音障害のリハビリ方法について詳しく紹介します。
おすすめ特集
構音障害の原因は?
構音障害の原因はさまざまですが、大きく分けて3つの要因が挙げられます。
● 運動性構音障害……発声・発語に関係する器官の「運動」が原因
● 機能性構音障害……発声・発語に関係する器官の「使い方」が原因
唇や舌などの声を出す器官が、奇形や欠損をしていると「器質的な原因」からうまく発音がしにくくなります。奇形や欠損がない場合でも、唇や舌がうまく動かせない「運動機能」が原因で正しく発音できないケースもあります。また、発声・発語に関係する器官に異常がないにもかかわらず、動かし方に問題があり正しく発音ができない「機能性」が原因の構音障害もあります。
上記の原因で構音障害が生じると、円滑なコミュニケーションが困難になるだけでなく、「自分の言いたいことが相手にうまく伝わらない」とストレスがたまってしまい、やりとりに消極的になってしまうことも。さらに、原因によっては「飲み込み」にも支障をきたす可能性もあるため、早期に検査を行ったうえで、症状に応じた適切なリハビリを行うことが大切です。
言語聴覚士が実践している構音障害のリハビリ内容

言語聴覚士は、定期的な検査結果に基づいて、患者さんの状態に応じた「個別のリハビリ内容」を考えます。構音障害の改善に向けて、言語聴覚士が実践しているリハビリは、主に「呼吸器官にアプローチするリハビリ」と「発声・発語の器官にアプローチするリハビリ」の2つが挙げられます。
呼吸器官にアプローチするリハビリは、声を出すための基礎となる呼吸機能の改善を目的に行うのが一般的です。たとえば、発声を中心とした呼吸法の練習や、呼吸が持続するための練習などがあります。
一方で、発声・発語の器官にアプローチするリハビリでは、発音や発話が明瞭になることを目的に行うケースが多いです。たとえば、唇や舌などの声を出す時に必要な器官の筋肉運動が挙げられます。
自宅でできる構音障害のリハビリ方法

前述した、言語聴覚士が実践しているリハビリは自宅でも行えます。ここからは、自宅でできる構音障害のリハビリ方法を紹介しましょう。
1.本の音読
本の音読は、構音障害のリハビリとして効果的な方法の1つです。好きな本や新聞の記事などを毎日10分程度、声に出して読むことで発音の流暢さや明瞭さの改善につながるでしょう。
始めは短い文章から、徐々に長い文章に挑戦するのがおすすめです。なお、音読をする際に、音声をボイスレコーダーで録音しておくと、後に改善の有無を確認できます。
2.歌唱
歌を歌うことは、楽しみながら呼吸と発声のコントロール練習ができる効果的なリハビリといえます。リズムにあわせて歌うことで、抑揚や高低が自然につけられるだけでなく、発話の流暢さの向上にもつながります。発音しにくい音がある場合は、事前に歌詞のなかにあるその音にマーカーをつけておき、歌う際に意識しながら歌えるとよいでしょう。
3.言語リハビリ用のアプリゲーム
スマートフォンやタブレットなどで利用できる言語リハビリ用のアプリゲームが開発されています。無料で使えるアプリゲームもあるため、気軽に楽しみながら発音や発語の練習ができるでしょう。
実際に言語聴覚士が実践するリハビリでも、アプリゲームを使用しながら行うケースもあります。活用したい場合には言語聴覚士に相談し、症状にあったアプリゲームを選ぶことをおすすめします。
小さい子どもでもできる構音障害のリハビリ方法
構音障害が気になるお子さんの場合、年齢によっては「まだ自分で音読やアプリゲームをするのは難しい」ということもあるでしょう。続いて、「小さい子どもでもできる構音障害のリハビリ」を紹介します。
1.シャボン玉・ラッパ遊び
シャボン玉やラッパのおもちゃを使った遊びは、口の形や呼吸方法などを自然に練習できるリハビリになります。シャボン玉でリハビリをする際は、泡の大きさを作り分けることで、呼吸コントロールが向上します。
ラッパのおもちゃを使ってリハビリをする際は、音の長さや強さを変えながら吹くことで細かな口の動きや呼吸コントロールを身につけられるでしょう。
2.ストローぶくぶく
コップに水を入れ、ストローを咥えて、息を水のなかに吹き込むことで「ぶくぶく」と泡を作る方法を用いると、口腔内の筋肉や呼吸コントロールの改善につながります。実施する際は、時間を計りながら行ってみましょう。決まった時間で呼吸を持続するように行うことで、自然に呼吸時間を調整する力が身につきます。なお、うまくできない場合は、ストローの太さや短さを変えることで、難易度の調整ができます。お子さんに合ったストローの種類を検討してみてください。
3.口じゃんけん
口の形を変えてじゃんけんをすることで、口腔内の筋肉量アップにつながります。口じゃんけんをする際は、下記のように口の形を変えてみましょう。
● チョキ:「い」の口
● パー:「あ」の口
お子さんがまだ小さく、口じゃんけんが難しい場合は、保護者の「マネ」をするだけでも、リハビリになります。口じゃんけんの顔を模倣してもらう以外に、「あっかんべー」といった唇や舌などを大きく動かす顔のマネをしてもらうのもおすすめです。
構音障害はリハビリによる早期改善が重要
構音障害は、「コミュニケーション」に支障をきたすため、リハビリによる早期改善が大切です。ただし、リハビリには本人のやる気が影響します。意欲を継続できるよう、無理なくリハビリを進めていきましょう。
また、構音障害の方とやりとりする際には、プレッシャーにならないような関わり方が大切です。相手が話している間は時間にゆとりを持って聞いたり、ジェスチャーといった非言語的要素も取り入れたりして「コミュニケーションが苦にならない」ための配慮を意識できるとよいでしょう。
>>【全国どこでも電話・メール・WEB相談OK】セラピストの無料転職サポートに申し込む
参考

tokoshi
言語聴覚士
回復期で失語症と高次脳機能障害を中心としたリハビリ業務に携わる。その後転職し、看取り施設で「最期の食事」を言語聴覚士として支援。現在は訪問リハビリやデイサービスでリハビリをしながらライターとしても活動しています。
他の記事も読む
- ストレッチポールでやってはいけないこと|理学療法士が解説
- 手根管症候群でやってはいけないことは?リハビリでの生活指導について解説
- 【仕事が辛い】言語聴覚士が病む原因とは?病む前に知っておきたい対処法も
- むち打ち症でやってはけないことは?むち打ち症の種類や治療法も紹介
- 福祉住環境コーディネーターの資格は役に立たない?セラピストにとってのメリットを解説
- 福祉住環境コーディネーターの仕事内容や年収は?資格取得をおすすめする人も解説
- 訪問リハビリは医療保険で利用できる?条件や注意点について解説
- パーキンソン病にリハビリは効果的!リハビリの具体的な方法と注意点・禁忌まで詳しく紹介!
- 高齢者に多い大腿骨頸部骨折!リハビリの流れと再発予防のポイントを解説
- 【失敗談】転職した言語聴覚士(ST)の失敗事例|転職で後悔しないための注意点を紹介
- 福祉用具専門相談員とはどんな仕事?なり方や向いている人などを解説
- 作業療法士必見!関わる機会が多い福祉用具の種類と選定のコツを解説
- 理学療法士と看護師のダブルライセンスのメリットは?取得の流れについて解説
- 理学療法士の男女比は?女性理学療法士が活躍している背景や今後の需要
- 下肢のMMTのやり方を解説|評価基準や実施中の注意点もご紹介
- 脳卒中に対するリハビリの流れを解説|リハビリの内容や重要性もご紹介
- 片麻痺に対するリハビリは?時期に応じた内容や自宅でのメニューをご紹介
- パーキンソン病のリハビリメニューとは?自宅で行える内容をご紹介
- 自宅でできる脳梗塞のリハビリ内容は?おすすめのリハビリサービスもご紹介
- 脊柱管狭窄症のリハビリ内容は?普段の生活での注意点も解説