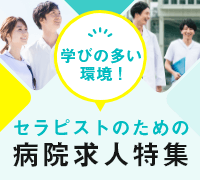高次脳機能障害の作業療法
公開日:2023.09.27

文:中山 奈保子
作業療法士(教育学修士)
おすすめ特集
「高次脳機能障害と作業療法」の現状
「高次脳機能障害」という言葉がまだ一般的ではなかったころ、脳の損傷により何らかの認知機能障害を負った方々とそのご家族は、納得がいく診断はもちろん、機能訓練や社会的サービスを受けることなく社会的に取り残されてしまうことが少なくありませんでした。
2001年に厚生労働省を中心に始められた「高次脳機能障害支援モデル事業」をきっかけに、高次脳機能障害を負った方々に対する診断、機能訓練から社会参加までの具体的な支援が整備されてきました。しかしながら、症状の複雑さや外見からは障害の重さが分かり難いといった特性上、まだまだ十分な理解には及んでいないのが実態と言えるでしょう。
私たち作業療法士は、対象者一人ひとりの障害をより丁寧に理解し、生活機能の改善に向けた治療・訓練だけではなく、対象者と社会生活をつなぐ橋渡し役のひとりとして、対象者ないしは身近な社会に働きかけることが求められます。
作業療法士の国家試験では、高次脳機能障害について以下のような問題が出題されています
《問題》2か月後の事務職への職場復帰を目的とした練習として適切なのはどれか。
【作業療法士】第57回 午前 8
25歳の女性。交通事故による外傷性脳損傷(右前頭葉)。職場復帰を希望している。WAIS-Ⅲでは言語性IQが76、動作性IQが106、全検査IQが89。RBMTが19点、TMT-Aが81秒、TMT-Bが90秒、BADSが104点、FIMが120点。対人交流は良好である。
2か月後の事務職への職場復帰を目的とした練習として適切なのはどれか。
- 1. 電話の受付
- 2. 企画書の作成
- 3. 書類の片付け
- 4. 会議の要約報告
- 5. 金銭の会計処理
解答と解説
正解:3
職場復帰を向けた作業療法では、対象者の障害特性や個人の特性、実際の生活環境と職場環境を把握し、解決すべき課題を明らかにしておくことが大切です。そのうえで、職場で実際に求められる作業の練習や代償手段の検討、環境の調整等を進めます。職場で求められる作業の練習では、高次脳機能の客観的な検査・評価結果に基づき、対象者の心身に過度な負担をかけることのないよう課題の難易度や実施頻度・時間・環境を設定します。
問題の症例は、動作性IQ(非言語的知能:知覚の統合・処理速度)が106であるのに対し、言語性IQ(言語的知能:言語理解・作業記憶)が76(境界域)、全検査IQが89(平均の下)であることから、上司や同僚とコミュニケーションをとりながら仕事を進めたり、考えてまとめたりといった思考力が求められる作業は難しい可能性がありそうです。
また、RBMT(リバーミード行動記憶検査)の結果が、軽度の記憶障害がありながらも復職を検討ができるレベルである一方で、TMT(Trail Making Test)の結果が標準より低く(A:30秒以下、B:64秒以下が標準)注意機能障害の傾向が認められます。このことから、注意力を要する作業を始めるのは、時期尚早であると判断できます。
そのため、1. 電話の受付、2. 企画書の作成、4. 会議の要約報告、5. 金銭の会計処理は、たとえマニュアル書が揃っていたとしても難しい可能性が高いです。たとえば、マニュアルに載っていない事案への即時対応(1)、全体を把握したり、思考力や情報処理力、注意・集中力を求められる作業(2や4)は、負担が大きいでしょう。5.会計処理のように、ひとつのミスが会社全体の損益に関わるような作業も復帰前の練習としては適しません。3の書類の片付けは、比較的難易度が低く、記憶・注意機能にアプローチしながらも身体を動かしながら進める作業のため適切と考えられます。
実務での活かし方 〜“ピア”の重要性〜
高次脳機能障害は、客観的な評価・検査結果だけでは、対象者が実際に直面する生活上の困りごとや不安感を理解するにはなかなか至りません。対象者自身も、もはや何に困っているのかわからなくなるほどど、予測不能な「困った」「なぜできない!?」に遭遇する日々を送っています。さらに言語障害が加われば、困りごとを伝えることも難しくなります。専門職だけではなく、高次脳機能障害の当事者同士による支え合い:ピアサポート(仲間としての支え合い)の場は、対象者と作業療法の目標を具体的に共有するうえで大切な機会となるでしょう。

中山 奈保子(なかやま なおこ)
作業療法士(教育学修士)。
1998年作業療法士免許取得後、宮城・福島県内の医療施設(主に身体障害・老年期障害)に勤務。
現職は作業療法士養成校専任教員。2011年東日本大震災で被災したことを期に、災害を乗り越える親子の暮らしを記録・発信する団体「三陸こざかなネット」を発足し、被災後の日常や幼くして被災した子どもによる「災害の伝承」をテーマに執筆・講演活動を行っている。
他の記事も読む
- 生活期における言語聴覚療法
- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント
- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法
- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導
- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について
- 赤ちゃんの座位発達段階について
- 糖尿病患者に対する適切な運動療法
- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション
- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?
- 二分脊椎と脊髄係留症候群について
- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応
- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい
- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入
- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法
- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション
- 大人の発達障害と作業療法
- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入
- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション
- アルツハイマー型認知症に合併する言語症状