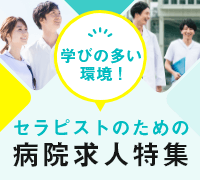生活期における言語聴覚療法
公開日:2024.03.15

文:近藤 晴彦
東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長
おすすめ特集
本記事の概要
今回取り上げる過去問のテーマは、「生活期における言語聴覚療法」についてです。
現在のリハビリテーションは、発症からの時期によって急性期・回復期・生活期の3期に分かれて展開されています。生活期のリハビリテーションの目的は、回復期のリハビリテーションによって獲得された能力の維持や、家庭や社会に適応して生活することを支援することにあります。
また、生活期のリハビリテーションでは「地域包括ケアシステム」が大きなテーマになります。地域包括ケアシステム構築のために、現在さまざまな取り組みが実践されています。
そこで今回は、言語聴覚士国家試験の過去問題から、生活期における言語聴覚療法に関する設問をピックアップし、詳しく解説します。
《問題》地域リハビリテーションについて誤っているのはどれか。
【言語聴覚士】 第25回 問題51
地域リハビリテーションについて誤っているのはどれか。
a.入所リハビリテーション――ADL訓練
b.組織化活動――保健、医療、福祉、介護、行政、地域住民の連携
c.通所リハビリテーション――医療保険の対象
d.訪問リハビリテーション――生活上の介護
e.教育啓発活動――介護教室
<選択肢>
- 1. a,b
- 2. a,e
- 3. b,c
- 4. c,d
- 5. d,e
解答と解説
正解:4
地域リハビリテーションは、障害者や高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活していくことを支える関係機関、関係者の関わり全般をさします。今回の設問ではa,b,eは正しい設問になりますが、c,dは誤りになります。
c.通所リハビリテーションは介護保険の対象であり、要介護認定者が対象になります。d.訪問リハビリテーションは、自宅を訪問しておこなう機能訓練やADL訓練をおこなうことであり、生活上の介護をおこなうのは訪問介護による取り組みになります。
実務での活かし方 ~生活期の言語聴覚療法のポイント~
生活期における言語聴覚療法について、(1)生活期の言語聴覚療法(2)地域包括ケアシステムにおける言語聴覚士の役割 の2つの観点から解説します。
(1)生活期の言語聴覚療法
生活期の言語聴覚療法では、日常生活における活動・参加の促進、生活環境の整備、介護負担の軽減などを中心に介入がおこなわれます。そのため、ICFの概念を用いた問題点の整理などが役立ちます。また、廃用症候群の予防を目的とした、予防的リハビリテーションをおこなうことも重要です。ここで注意が必要な点は、生活期の言語聴覚療法においても、機能的な訓練をおこなうことが重要だということです。失語症などの高次脳機能障害は、発症から比較的時間が経過しても、機能的な改善が認められることが知られています。そのため、生活期においてもこれらの改善を目的とした介入をおこなうことが重要です。
(2)地域包括ケアシステムにおける言語聴覚士の役割
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするための、介護・医療・住まい・生活支援・介護予防を充実させるためのシステムのことです。団塊の世代が75歳以上となる2025年以降は医療や介護の需要が急増することが見込まれるため、2025年を目途に構築されることを目指しています。
地域包括ケアシステムにおける言語聴覚士の役割として、介護予防と生活支援を実施することが求められます。予防的な観点での介入には、誤嚥性肺炎など摂食嚥下障害への介入や栄養や筋力といったフレイルへの介入、難聴への介入、閉じこもりなどのコミュニケーションへの介入といった幅広い介入が求められています。
まとめ
生活期における言語聴覚療法について解説しました。生活期では、活動・参加の促進や予防的な観点から介入を行うことが重要です。また、2025年までに構築されることを目指す「地域包括ケアシステム」において、言語聴覚士は専門職としては幅広い介入を行うことが期待されています。
[出典・参照]
半田理恵子ら.標準言語聴覚障害学 地域言語聴覚療法学.医学書院,2019
藤田郁代ら.標準言語聴覚障害学 失語症学 第3版.医学書院,2021

近藤 晴彦(こんどう はるひこ)
東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長
国際医療福祉大学大学院 修士課程修了。
回復期リハビリテーション病院に勤務する言語聴覚士。
 東京都言語聴覚士会
東京都言語聴覚士会
http://st-toshikai.org/
東京都におけるすべての言語聴覚士が本会に入会され、自己研鑽に励み、地域社会に貢献することを目指し、活動中。
他の記事も読む
- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント
- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法
- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導
- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について
- 赤ちゃんの座位発達段階について
- 糖尿病患者に対する適切な運動療法
- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション
- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?
- 二分脊椎と脊髄係留症候群について
- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応
- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい
- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入
- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法
- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション
- 大人の発達障害と作業療法
- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入
- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション
- 高次脳機能障害の作業療法
- アルツハイマー型認知症に合併する言語症状