理学療法士養成校の学生がブラインドサッカー選手になるまで
公開日:2017.08.18 更新日:2021.08.23
「見えない」人たちが全力でするサッカーは想定外の迫力

私は小学生の頃からサッカーをしていました。そうした中でブラインドサッカーを初めて知ったのは、横浜リハビリテーション専門学校時代に代表チームの合宿を見学したことがきっかけです。
視覚障害のある選手たちは、当然ですがボールやピッチの様子を見ることができません。ですから「障害のない選手のスポーツとは違う」と自分のなかで線を引いていました。サッカーといっても目の見えない人たちがゆっくり動いている感じだろうと想像していました。
ところが実際に練習を見て、想像との違いにとても驚きました。選手は全力で走るし、身体がぶつかり合うコンタクトプレーもすごい迫力。自分の想定よりもはるかに上をいく激しいスポーツでした。選手たちはボールが見えているかのように走り、パスをして、ドリブルからシュートを決めました。
ブラインドサッカーは視覚障害者のスポーツのなかでも特殊だと思います。ネットを挟んで対戦するのではなく、相手との接触があります。そうした相手をかわしてボールをゴールまで運ぶ動きは、私がイメージしていた「視覚障害者」を超える激しさでした。
視覚障害の世界を知るきっかけに
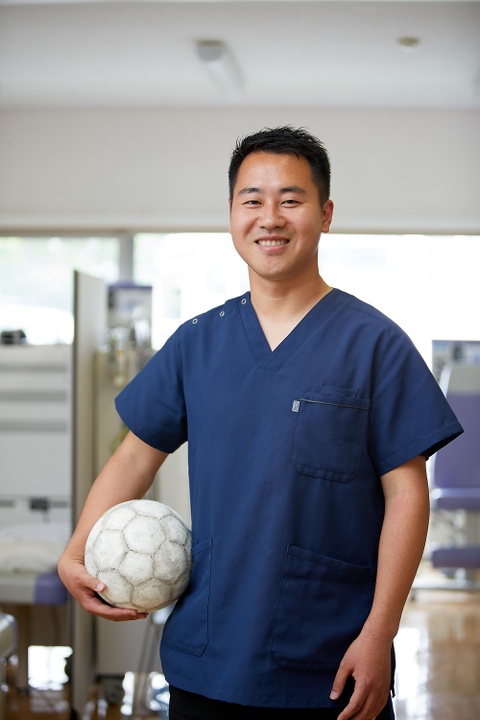
その後、これまでのサッカー経験を買われ、八王子を拠点に活動しているブラインドサッカーチーム「たまハッサーズ」でのプレーに誘われます。実際に選手たちとプレーしてみると、視覚障害者は自分が思っていたような「何もできない」人たちではありませんでした。
手助けを必要とすることもあるけれど、大抵のことは自分でできます。もちろん選手にもよりますが、練習でも手取り足取りサポートするような必要はなく、状況を言葉で説明するだけで理解できます。サッカーに限らず生活面でも、私はこれまで視覚障害者にとても低いレベルで線を引いてしまっていたことに気づかされました。
視覚障害者が頭のなかでどのように周囲の状況をイメージしているのか、それは先天性障害と見えていた経験のある中途障害でも違うようです。サッカーでボールやプレイヤーの位置をイメージするような空間認知は先天性障害の選手の方が長けているかもしれません。
私は当初、ゴールキーパーとして参加しましたが、今はアイマスクを装着してプレーヤーとしてプレーしています。何も見えない状態ではピッチでの各選手の位置、自分が思い描いているピッチのイメージ、さらに他の選手の思い描くイメージが一致しなければチームプレーができません。それが難しさであり、面白さでもあります。
2010年シーズンにはゴールキーパーの強化指定選手として日本代表チームの選考合宿に参加しました。そして2011年に代表チームのスタッフにならないかと声をかけていただきました。2012年からはコーチとして代表チームに携わり、2016年からはブラインドサッカー協会のメディカルスタッフとして日本代表合宿や日本選手権で仕事しています。(次回へ続く)
他の記事も読む
- 車椅子バスケ~障害者スポーツだからこそ、理学療法士の専門性が生きてくる
- ルール次第で重度障害者アスリートが主役に。車椅子バスケ大会、High8(ハイエイト)
- 障害者のスポーツ経験は生活の自立につながる
- 理学療法士がサポートするとスポーツ選手は強くなれるのか
- 世界トップのブラジル代表チームで活躍する理学療法士
- 日本代表チームのメディカルスタッフとして金メダルを目指す
- ブラインドサッカー、日本代表選手の高度な空間認知能力に驚き
- スポーツのリハビリテーションは競技知識が必須です
- テニスのジュニア選手から理学療法士を目指すまで
- 海外パラ選手の障害に配慮しないハードな練習にビックリ
- 理学療法的な視点から代表選手の選考に携わる経験も
- 視覚障害者に「どれくらい見えますか?」と聞けなかった
- スポーツリハ職員、ゴールボールの代表チームトレーナーになる
- 競技経験があるからこそ選手のことを理解できる スポーツがリハビリテーションの可能性を広げます
- 高度化する障害者スポーツは危険なのか? 理学療法士は障害特性を理解した指導ができる
- めざせ東京パラリンピック出場 夢への第一歩、東京都の選手発掘プログラム
- 9月8日開幕! セラピスト的パラリンピックは障害者スポーツ補装具に注目
- 障害者水泳、成田真由美選手復活! 日本記録更新でパラリンピックへ
- 男女混成のバトル系種目、車椅子ラグビーは重度障害者スポーツ!?
- 車椅子バスケはリオパラリンピックで世界に挑む
















