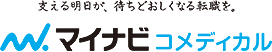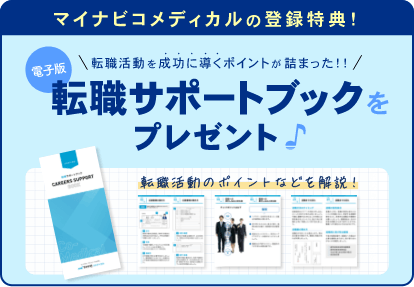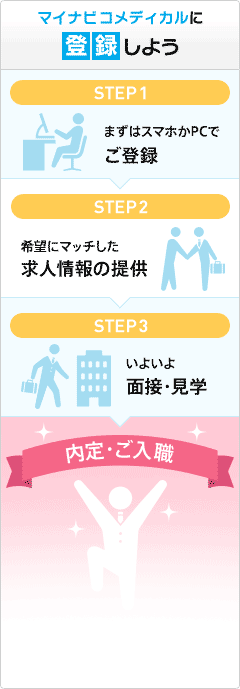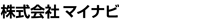言語聴覚士は副業を行える?メリット・注意点とおすすめの副業を紹介
先行きが見えにくいことから、「収入源は複数あったほうが良い」と言われるようになった近年、副業を始める言語聴覚士の方も少しずつ増えているようです。
副業には、「本業以外の収入を得られる」というほかにもさまざまなメリットがあります。しかし、自分のスタイルや考え方に合わない仕事を選ぶと、思ったほどの収入が得られないばかりか、心身に大きな負担がかかったり、長続きしなかったりする可能性もあります。まずは「自分に合った副業」を探すことから始めましょう。
当記事では、言語聴覚士が副業を行うメリットから、言語聴覚士におすすめの副業、副業を始める際の注意点までを詳しく紹介します。副業に少しでも興味のある言語聴覚士の方は、ぜひご一読ください!
転職のプロにお気軽にご相談ください♪(完全無料)

目次
言語聴覚士が副業を行うメリット
現在、日本政府は「働き方改革」として、社会人が理想の働き方を柔軟に選択できる環境づくりに取り組んでいます。働き方改革ではこれまで、雇用形態による待遇の格差や長時間労働の是正など、さまざまな取り組みが行われてきましたが、そのなかでも従来と大きく変わったのが「副業・兼業の促進」です。
(出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」/https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf)
ここでの副業・兼業とは、本業以外の仕事も掛け持つことを指します。以前、副業は多くの企業で認められていませんでしたが、政府が副業を推奨するようになったことで、社員の副業を認める企業が増加。働く人が複数の収入源をもつことが容易となりました。
現在では、業種を問わず副業を始める方も多くいます。では、言語聴覚士が副業を行うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
| 言語聴覚士が副業を行うメリット |
|---|
|
●収入が増える (出典:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」/https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html) 副業を始めれば収入が増え、収入が増えれば本業においても、心に余裕をもって働くことができるようになるでしょう。 ●仕事の視野が広がる |
現役言語聴覚士にインタビュー
言語聴覚士におすすめの副業
言語聴覚士のできる副業には、本業での業務内容やスキルを生かせるものからそうでないものまで、さまざまな種類があります。仕事の種類によって働き方も大きく異なるため、下記を参考に「自分に合った副業」かどうかをチェックしておくと良いでしょう。
- ●本業に支障をきたさないか
- ●「さらなるスキルアップ」と「さらなる収入増」のどちらを重視するのか
特に大切なのが、本業に支障をきたさないかどうかです。副業の勤務時間と本業の勤務時間が被るのはもちろんNGですが、たとえ時間が被っていなくても、副業の労働時間が長すぎたり、副業でエネルギーを使いすぎたりするのは考えものです。本業がおろそかにならないように、十分注意しましょう。
ここからは、言語聴覚士におすすめできる副業をいくつか紹介します。
非常勤のアルバイトをする
言語聴覚士におすすめの副業が、非常勤アルバイトです。非常勤であればシフトや労働時間の自由度が高いため、本業の忙しさや負担を考慮しつつ働くことができ、長続きもしやすいでしょう。
本業で言語聴覚士として働いているのであれば、非常勤アルバイトでも訪問リハビリテーションやデイサービス(通所介護)を選ぶのがおすすめです。訪問リハやデイサービスの非常勤アルバイトは、週1日から働ける職場が多いほか、本業で培ったスキルも存分に生かせます。加えて、本業とは異なる環境で知識・技術の幅を広げることも可能です。
言語聴覚士が、副業として訪問リハやデイサービスでの非常勤アルバイトを始める場合は、本業に支障をきたさないよう、体調管理に気を付ける必要があります。前述したように、週1日1時間勤務から応募できる施設も多いため、そうした柔軟性の高い求人を選ぶと良いでしょう。
言語聴覚士の非常勤・パート求人を探す
独立して訓練やセミナーを行う
言語聴覚士は、患者さまの「言語訓練」「構音訓練」を医師の指示なしで行うことができます。言語聴覚士としてのスキルを生かすだけでなく、キャリアアップ・キャリアチェンジにもつながる副業がしたい場合は、独立して患者さまに自ら言語訓練・構音訓練を提供するのも一案です。なお、「嚥下訓練」「聴力検査」「補聴器装用訓練」は医師の指示が必要となるため、独立しても訓練は提供できません。
独立と聞くと忙しいイメージを抱く方もいそうですが、実際に専門知識を生かして独立し、本業の合間(休みの日など)に開業したり、空いた時間にセミナーを行ったりする言語聴覚士も多くいます。
ネットでできる副業を行う
ネットでできる副業は言語聴覚士に限らず人気で、仕事内容としては、「Webライター」や「アフィリエイト」などが挙げられます。空いた時間を使って作業できるため、本業とのスケジュール調整がしやすい点や、自宅にパソコンとネット環境があればすぐに始められる点などが大きな魅力です。
ネットで副業をする場合のポイントは、本業に関連するテーマを選ぶことです。例えばWebライターとして活躍する場合、言語聴覚士の知識や専門性を生かして記事を書いたり、専門家の視点から記事の監修を行ったりすると良いでしょう。
趣味を活かした副業を行う
「副業を始めたいけれど、本業の忙しさを考えると負担の多い仕事はなるべくやりたくない」「積極的に取り組める副業がしたい」という方は、自分が楽しいと思える趣味を生かした副業を行うのがおすすめです。
一般的に多く見られるものとしては、ハンドメイド作品や撮影した写真データの販売などが挙げられます。趣味を生かした副業であれば、楽しんで取り組めるため長く続けられるでしょう。また、ネット副業と同様に空いた時間を有効に使えるため、本業とのスケジュール調整もしやすくなります。
転職のプロがアドバイスします♪(完全無料)
言語聴覚士が副業をするときの注意点
言語聴覚士が副業を始める際は、いくつか気を付けなければならないポイントも存在します。特に注意が必要なのは、「勤務している職場では副業が認められているかを確認すること」、そして「必要に応じて確定申告を行うこと」の2点です。
最後に、それぞれの注意点をより詳しく説明します。
副業可の職場か確認する
国が副業や兼業を推奨し始めたことで、社員の副業を認める企業も増加しました。しかし、就業規則で副業を禁止している職場は、現在でも少なくありません。副業を具体的に検討する前に、必ず就業規則を確認しましょう。
副業が禁止されている場合は、当然副業を行ってはなりません。それでも副業をしたいという場合は、副業を許可している職場への転職を検討するのも1つの手段です。
言語聴覚士の求人を探す
なお、たとえ副業OKの職場であっても、副業に精を出しすぎて本業に影響が出るのは本末転倒です。「本業には普段通り取り組む」ということを念頭に置いて、副業の仕事量を調整することが重要でしょう。
確定申告を行う
給与以外の所得、つまり副業の収入から経費などを引いた額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得額を計算し、国に収めるべき税金の総額を確定させる手続きのことです。
医療機関や企業に雇用され、副業せずに働いている場合は、給与収入が2,000万円を超えない限り確定申告の必要はありません。しかし、副業を本格的に始めれば、確定申告の義務が生じる可能性も十分にあります。20万円以上の副業所得があるのに確定申告を行わなかった場合、「無申告」とみなされて無申告加算税が課されるため、忘れないよう注意しましょう。
(出典:国税庁「副収入などがある方の確定申告」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm)
キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)
まとめ
ダブルワークOKの企業や副業先としての応募を歓迎する企業が増加している現在、副収入の獲得やさらなるスキルアップを目指して、副業を始める言語聴覚士も増えています。
言語聴覚士の方におすすめの副業は、「非常勤アルバイト」「独立(訓練の提供・セミナーの開催)」「ネット関連の副業」「趣味や経験を生かした副業」などです。一口に副業といっても、それぞれに働き方が異なるため、本業の仕事内容や労働時間、体力的な余裕、勤務地を考慮して、自分に合った副業を選びましょう。
また、単純に年収をアップさせたい場合は、転職を検討してみるのもおすすめです。医療介護専門の求人サイト「マイナビコメディカル」では、全国の言語聴覚士の求人を多数掲載しています。転職に少しでも不安のある言語聴覚士の方は、言語聴覚士業界に精通したキャリアアドバイザーによる転職支援サポートを、ぜひご利用ください!
転職のプロと考えていきましょう!(完全無料)
職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する
※当記事は2022年9月時点の情報をもとに作成しています
監修者プロフィール

マイナビコメディカル編集部
リハ職・医療技術職・栄養士のみなさまの転職に役立つ情報を発信中!
履歴書や職務経歴書の書き方から、マイナビコメディカルサイト内での求人の探し方のコツや、転職時期ごとのアドバイス記事などを掲載。
転職前の情報収集から入職後のアフターフォローまで、転職活動の流れに添ってきめ細やかなフォローができる転職支援サービスを目指しています。