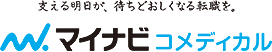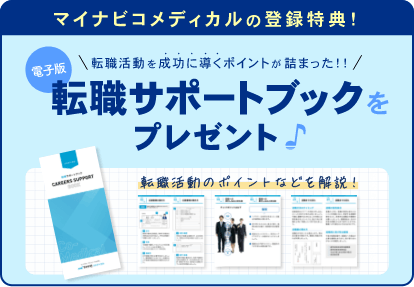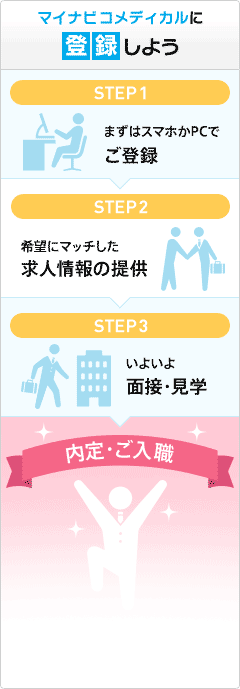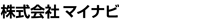臨床工学技士の国家試験の詳細|日程から出題される科目まで
更新日 2023年11月19日 公開日 2021年08月27日
#情報収集血液透析装置や人工呼吸器、人工心肺装置といった高度な医療機器のスペシャリストである臨床工学技士は、チーム医療の現場において欠かせない存在です。一般的に臨床工学技士の資格を取得するには、大学・短大・専門学校などで専門課程を修了した後、国家試験に合格する必要があります。
「臨床工学技士は独学でもなれる?」という疑問を持っている方もいるかもしれませんが、学校で学ぶことが受験資格を得る条件となっているため、完全独学で臨床工学技士の資格取得を目指すことはできません。また、国家試験は9科目の広範囲から出題されることから、合格に向けては入念な試験対策が必要です。
今回は臨床工学技士の国家試験を取り上げ、受験資格や日程、出題される科目、難易度、合格を目指すための対策などを詳しく解説します。臨床工学技士を目指している方はもちろん、臨床工学技士に興味のある方もぜひ参考にしてください。
転職のプロと考えていきましょう!(完全無料)
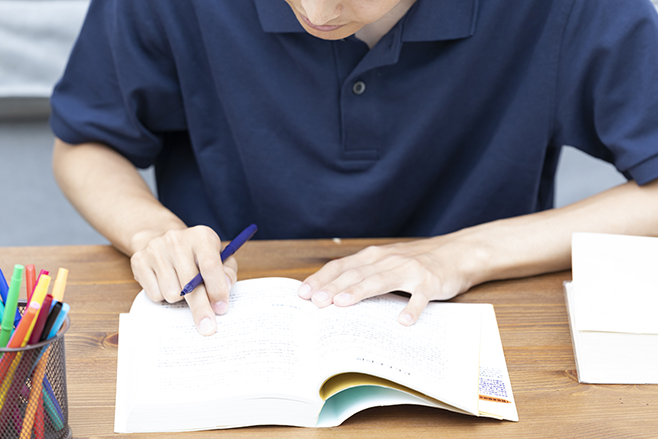
目次
臨床工学技士の国家試験の受験資格
臨床工学技士になるには、国家試験に合格した上で臨床工学技士免許を取得しなくてはなりません。臨床工学技士国家試験の受験資格は、以下に示すいずれかのルートで得られます。
| (1)高等学校卒業者 ●大学入学資格のある者 |
||
|---|---|---|
| 下記の学科いずれかを卒業する | ||
| 大学(4年制) | 短大(3年制) | 専門学校(3年制) |
| 臨床工学科 医用電子工学科 など |
臨床工学科 | 臨床工学科 |
| (2)大学・短大・専門学校・養成校などの在校者・卒業者 ●2年以上修業済み(高等専門学校は5年)で、厚生労働大臣の指定する科目を修了した者 |
|---|
| 文部科学大臣が指定した学校・都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所で、1年以上修業し、臨床工学技士として必要な知識・技術を取得する |
| (3)大学・短大・専門学校・養成校などの在校者・卒業者 ●1年以上修業済み(高等専門学校は4年)で、厚生労働大臣の指定する科目を修了した者 |
|---|
| 文部科学大臣が指定した学校・都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所で、2年以上修学し、臨床工学技士として必要な知識・技術を取得する |
| (4)大学の在校者 |
|---|
| 厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業する |
| (5)外国の教育機関で条件を満たした者・免許取得者 ●外国の生命維持管理装置の操作・保守点検に関する学校・養成所の卒業者 ●外国で臨床工学技士免許に相当する免許を取得した者 |
|---|
| 厚生労働大臣から、他の受験資格取得者と同等の知識・技能を有すると認定される |
(出典:厚生労働省「臨床工学技士国家試験の施行」/https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukougakugishi/)
臨床工学技士国家試験の受験資格を得るには、大学や短大、専門学校などに進学した上で、専門的な知識と技術を学び、修了する必要があります。なお、すでに看護師や臨床検査技師などの医療資格を保持している場合は、(2)(3)の条件に該当します。
日程と受験地
臨床工学技士の国家試験は年に1度、3月に実施され、合否の発表も同月中に行われます。なお、試験会場は北海道・東京都・大阪府・福岡県の4か所のみとなっています(2023年時点)。
| 試験予定日 | 3月上旬 |
|---|---|
| 試験会場 | ●北海道 ●東京都 ●大阪府 ●福岡県 |
| 合否確認 | 下記のホームページに受験地・受験番号が掲載される ●厚生労働省ホームページ:資格・試験情報のページ ●公益財団法人医療機器センターホームページ |
| 合格発表日 | 3月下旬 |
| 願書提出期間 | 12月上旬~1月上旬 |
| 受験手数料 | 30,800円(口座振り込み) |
(出典:厚生労働省「臨床工学技士国家試験の施行」/https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukougakugishi/)
資格取得に向けた進学先と取得後の認定制度
臨床工学技士の国家試験で出題される科目
臨床工学技士の国家試験は午前と午後の2部構成で行われ、9科目から全180問出題されます(1問1点/マークシート方式)。下記は、臨床工学技士の国家試験で出題される科目とその概要です。
| 科目 | 科目における主な出題概要 |
|---|---|
| 医学概論 (公衆衛生学・人の構造・機能・病理学概論・関係法規を含む) |
<主な出題範囲> ●呼吸 ●循環 ●泌尿器 ●胸部外科 <少数出題> ●脳神経 ●消化器 ●内分泌 ●感染症 |
| 臨床医学総論 (臨床生理学・臨床生化学・臨床免疫学・臨床薬理学を含む) |
|
| 医用電気電子工学 (情報処理工学を含む) |
●交流を含む電気回路の基本 ●増幅器 ●センサの基本 ●機械要素 ●機械に関する基礎力学 ●流体に関する基礎力学 ●関連する物理現象 |
| 医用機械工学 | |
| 生体物性材料工学 | ●生体の特性について ・電気的特性 ・力学的特性 ・機械的特性 ●特殊な使用材料について ・人工透析 ・人工心肺 ・人工血管 |
| 生体機能代行装置学 | ●臨床工学技士業務に使用する機器について ・人工透析装置 ・人工心肺装置 ・人工呼吸装置 ・高気圧酸素療法装置 ・他関連機器 |
| 医用治療機器学 | ●ペースメーカー ●電気メス ●大動脈バルーンポンピング装置 ●レーザー治療器 ●超音波メス |
| 生体計測装置学 | ●心電計 ●血圧計 ●パルスオキシメータ ●筋電計 ●脳波計 |
| 医用機器安全管理学 | ●医療機器の電気事故 ●医療ガスの事故を防止する法令 ●安全管理方法 |
(出典:厚生労働省「臨床工学技士国家試験の施行」/https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukougakugishi/)
(出典:一般社団法人日本臨床工学技士教育施設協議会「どんな試験なの?」/http://www.jaefce.org/test_ce/what_test/)
魅力・やりがいから資格の取得方法まで
臨床工学技士の国家試験の合格率・難易度は?
臨床工学技士の国家試験における2017年~2022年の合格率は、下記のとおりです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 2,947名 | 2,413名 | 81.9% |
| 2018年 | 2,737名 | 2,017名 | 73.7% |
| 2019年 | 2,828名 | 2,193名 | 77.5% |
| 2020年 | 2,642名 | 2,168名 | 82.1% |
| 2021年 | 2,652名 | 2,232名 | 84.2% |
| 2022年 | 2,603名 | 2,096名 | 80.5% |
(出典:厚生労働省「第30回臨床工学技士国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2017/siken17/about.html)
(出典:厚生労働省「第31回臨床工学技士国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2018/siken17/about.html)
(出典:厚生労働省「第32回臨床工学技士国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2019/siken17/about.html)
(出典:厚生労働省「第33回臨床工学技士国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2020/siken17/about.html)
(出典:厚生労働省「第34回臨床工学技士国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2021/siken17/about.html)
(出典:厚生労働省「第35回臨床工学技士国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2022/siken17/about.html)
臨床工学技士の国家試験における合格基準は、180点中108点(正答率6割)以上となっています。
データからも分かるように、過去6年間における全体の合格率は80%前後で推移しており、合格率が大きく変動することはありませんでした 。臨床工学技士は高度な知識と技術が求められる国家資格ですが、学校のカリキュラムを真剣に学び、日々試験の対策を行っておけば十分に合格できる難易度と言えるでしょう。
収入アップの方法や仕事の将来性も解説
臨床工学技士の国家試験に合格するための対策2つ
臨床工学技士の国家試験は、飛びぬけて難しい内容が出題されるわけではありません。ただし、出題範囲が広いため、合格の可能性を高めるには早い時期から試験対策を講じることが重要です。
ここでは、臨床工学技士の国家試験に合格するための対策を2つ紹介します。
過去問を解く
臨床工学技士の国家試験対策では、過去問の反復練習と分析が重要となります。
先に紹介したように、臨床工学技士の試験問題は広範囲から出題されるため、まずは「問題を解くこと」に慣れる必要があります。幅広い知識を身に付け、全体的な試験の出題傾向を把握するためにも、「最低過去5年分」を目安に過去問に取り組みましょう。
過去問に取り組む際は、間違えた問題の解説を正答できるまで読み込むなど、きちんと分析することが大切です。過去問をすべて解き終えたら最初からやり直し、苦手な分野を克服してください。
試験では既出の問題とほぼ同じ内容の問題が出題されることもあるため、過去問を徹底的に分析することで、出題されそうな問題を予測できるケースもあるでしょう。
得意分野を徹底的に復習する
幅広い分野が出題される臨床工学技士の国家試験では、苦手分野に時間をかけすぎないのも1つの戦略です。特に試験の日程が近付いている場面では、焦って苦手分野に取り組むよりも、得意分野を徹底的に復習したほうが、正答率アップの可能性は高まります。
臨床工学技士の国家試験に合格する正答率の目安は、60%以上とされています。不得意な分野を除いた出題範囲で、60%以上の正答率が期待できる場合には、得意分野を完ぺきに仕上げることを優先しましょう。
得意分野を固めた上で不得意分野の底上げに取り組めば、気持ちにも余裕が生まれるはずです。
臨床工学技士の求人を探す
まとめ
臨床工学技士になるためには養成校で専門課程を修了した後、国家試験に合格しなければなりません。臨床工学技士の国家試験は年に1度実施され、医学概論、医用電気電子工学、医用機械工学、生体機能代行装置学などの科目から全180問が出題されます。
臨床工学技士国家試験の合格率は例年80%前後で推移していますが、難易度が低いわけではなく出題範囲も広いため、早くから対策を行うのがおすすめです。
合格を目指すには、過去問の反復練習と分析が大事です。間違えた問題の解説を正答できるまで読み込むなど、きちんと分析することで幅広い知識を身に付けましょう。また、不得意な分野を除いた出題範囲で、合格基準をクリアできそうな場合には、得意分野を徹底的に仕上げるのも1つの戦略です。
キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)
職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する
※当記事は2022年5月現在の情報を基に作成しています
監修者プロフィール

マイナビコメディカル編集部
リハ職・医療技術職・栄養士のみなさまの転職に役立つ情報を発信中!
履歴書や職務経歴書の書き方から、マイナビコメディカルサイト内での求人の探し方のコツや、転職時期ごとのアドバイス記事などを掲載。
転職前の情報収集から入職後のアフターフォローまで、転職活動の流れに添ってきめ細やかなフォローができる転職支援サービスを目指しています。