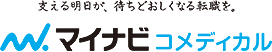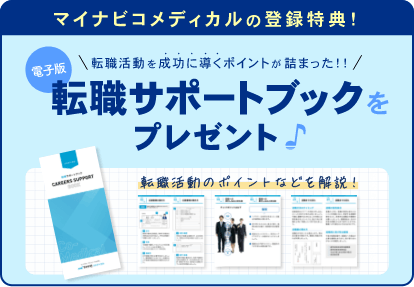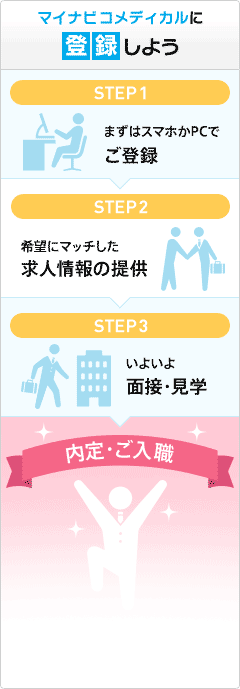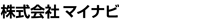言語聴覚士が働く場所は?代表的な4つの就職先と知っておきたいこと
言語聴覚士の仕事は、言葉によるコミュニケーションが難しい方、あるいは食べたり飲み込んだりすることがうまくいかない方をサポートすることです。患者さま、利用者さまが抱えている障害は、病気や事故によるものから、発達上の問題に関わるものまでさまざまです。
言語聴覚士の有資格者が活躍できる場所は、医療施設だけに限りません。介護福祉施設、保険施設、教育機関、企業などさまざまな選択肢があるため、自身のキャリアプランやライフスタイルに合った職場を選びましょう。当記事では、言語聴覚士の代表的な就職先を4つ挙げ、それぞれの特徴や就職する上で知っておきたい情報をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
転職のプロがアドバイスします♪(完全無料)

言語聴覚士の代表的な就職先4つ
言語聴覚士は、病気やけがが原因で言語、聴覚、発声・発音、認知などに問題を抱える方をサポートすることもあれば、加齢による摂食・嚥下などの機能低下をサポートすることもあり、働く場所はさまざまです。
以下では、代表的な言語聴覚士の就職先を4つご紹介します。
医療機関
医療機関は、多くの言語聴覚士が働く場所です。総合病院、大学病院のほか、専門病院、クリニックなどさまざまな規模の医療機関で言語聴覚士が求められています。医療機関で働く言語聴覚士は、リハビリテーション科だけでなく、耳鼻咽喉科、形成外科、口腔外科、小児科などさまざまな診療科で、幅広い年齢層の患者さまと接することになるでしょう。
言語聴覚士が医療機関で働く場合の特徴は、下記のとおりです。
| 医療機関勤務の特徴 |
|---|
| ・言語聴覚士の約7割が医療機関で働いている ・施設の特性や診療科によってリハビリの内容が異なる ・チーム医療を通じて多くのスタッフと関わる ・社会復帰のための相談や支援も行う ・医療機関によっては在宅医療に参加することもある |
2021年3月時点で、言語聴覚士の約7割が医療機関に勤務しています。前述の通り、数多くの施設や診療科で需要がある上に、近年は在宅医療の場においても言語聴覚士が求められているため、今後も高い水準で需要が推移すると考えて良いでしょう。
(出典:日本言語聴覚士協会「言語聴覚士とは」/https://www.japanslht.or.jp/what/)
業務内容は医療機関の特性によって異なります。たとえば救急外来が多い大学病院などでは、急性期にあたる患者さまと関わる機会が多く見られます。回復期に移行すると、患者さまの多くは専門病院やリハビリテーションセンターへ移るため、そうした施設で働く言語聴覚士の業務は、回復期向けの内容が中心となります。
患者さま1人ひとりの状況に合わせたリハビリや、社会復帰のための相談などに従事して、幅広い仕事を経験したい方、あるいはスキルアップを目指したい方は、医療機関勤務に向いているでしょう。
介護福祉施設
介護福祉施設には、食べ物をうまく飲みこめない摂食・嚥下障害のリスクを抱えた方や、認知症の方などがいらっしゃるため、医療機関に次いで多くの言語聴覚士が活躍しています。老人ホームをはじめとする入居施設はもちろん、デイサービスセンターのような通所施設においても、言語聴覚士による訓練、指導、介助が必要とされています。
言語聴覚士が介護福祉施設で行う業務の特徴は、下記の3つです。
| 介護福祉施設勤務の特徴 |
|---|
| ・摂食・嚥下障害の利用者さまのサポートが多い ・障害の原因が病変や損傷ではなく、加齢の場合も多い ・単純な機能回復だけでなく、食べる喜びを取り戻す業務も求められる |
高齢になると摂食・嚥下の機能が低下するだけでなく、気管に異物が入り込んだ際に排出する反射機能も衰えます。気管に入った食べ物などが原因で誤嚥性肺炎を引き起こすと、最悪の場合命に関わるため、注意が必要です。
介護福祉施設で働く言語聴覚士は、摂食・嚥下障害に悩まされる方や予防が必要な方などを訓練、指導によってサポートします。現在、高齢化が急速に進行していることを考えれば、言語聴覚士の需要がさらに高まる職場と言えるでしょう。
介護福祉施設では、リハビリを兼ねたレクリエーション企画を担当することもあるため、専門知識に加えて発想力のある方に向いています。就職先によっては認定言語聴覚士の資格を持っていると、より専門性の高いサポートができるでしょう。
介護福祉施設&訪問リハビリ(在宅医療)勤務の言語聴覚士求人を探す
子どもの福祉施設・教育機関
言語聴覚士は、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、子どものための福祉施設で働くこともできます。また、教員免許を取得して、一般の小中学校や特別支援学校の教員として働く方もいます。
子どもの福祉施設・教育機関の特徴として、下記の4つが挙げられます。
| 子どもの福祉施設・教育機関 |
|---|
| ・さまざまな障害を抱えた子どもを担当する ・学習面や生活面での指導も含むことがある ・遊びを取り入れるなど訓練に工夫が求められる ・幼稚園や保育所を支援する場合もある |
子どもがスムーズにコミュニケーションを取れない原因は、発達障害や知的障害、自閉症などさまざまです。子どもの福祉施設・教育機関で働く言語聴覚士は、1人ひとりに合わせた訓練、指導に加えて、生活サポートや学習サポートなども行います。
訓練自体に興味を持ってもらえるように、遊びを取り入れたり、楽しい雰囲気をつくったりする工夫が求められるため、子どもとのコミュニケーションが好きな方、子どもとのコミュニケーションに自信のある方に向いています。
施設によっては、聴覚障害を持つ子どもを担当するケースもあるため、手話通訳士などの資格を取得しておくと、就職・転職で有利になる可能性があります。
また、言語聴覚士の養成校で教職員の人材募集が行われることもあるので、興味のある方は、出身校に職員募集がないかを問い合わせてみると良いでしょう。
保育園&小児リハビリ勤務の言語聴覚士求人を探す
保健所・保健センター
医療機関や介護福祉施設に比べて割合は低いものの、地方自治体が運営する保健所や保健センターも言語聴覚士が働く施設の1つです。
言語聴覚士が保健所・保健センターで働く場合の業務内容、職場環境などに関する特徴は、下記の通りです。
| 保健所・保健センター勤務の特徴 |
|---|
| ・相談業務を担うことが多い ・子育て関連の相談窓口が設けられている施設もある ・収入が安定的で福利厚生も充実している |
保健所や保健センターで働く言語聴覚士は、公務員待遇となるため収入が比較的安定しており、福利厚生も充実しています。そのため非常に人気がありますが、求人数自体は少ない傾向です。
言語聴覚士が保健所や保健センターで働く場合は、相談業務が主な業務となります。身近な悩みから、病気や事故の後遺症に関する悩みまで、相談内容は多岐にわたるため、幅広い知識が求められるケースも多いでしょう。
(出典:一般社団法人日本言語聴覚士協会「言語聴覚士とは」/https://www.japanslht.or.jp/what/)
仕事内容や働く場所を解説
言語聴覚士を目指す方が知っておきたいこと
言語聴覚士を目指す方は、将来働く場所の選択肢に加えて、今後の需要や資格以外に求められる能力についても、知っておくと良いでしょう。医療機関以外にさまざまな施設で活躍できるため、言語聴覚士以外の経験やスキルが役立つ場合も少なくありません。
ここでは、言語聴覚士の現在の需要から見る将来性と、資格以外に必要とされる能力についてご紹介します。
言語聴覚士の需要と将来性
2016年に厚生労働省が発表した資料によると、言語聴覚士の人数は以下の通りでした。なお、調査対象は全国約1,000施設となっています。
・病院で働く言語聴覚士:3,124人
・介護保険施設などで働く言語聴覚士:315人
年齢別で見ると20歳~40歳の年齢層が最も多く、どちらの施設でも全体の8割程度を占めています。
(出典:厚生労働省「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士需給調査」/https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120212_6.pdf)
また、「言語聴覚士の人員数は充足しているか」との質問に対しては、「基準上は充足している」と答えた施設が82.1%を占めたものの、「運営上(患者の状況に応じて必要な人員)充足している」と回答した施設は41.3%にとどまっています。多くの施設が設置すべき人員基準を満たしている一方で、半数以上の施設が「患者さまへのリハビリを提供する上で十分な言語聴覚士を確保できていない」と感じている点に、注意が必要でしょう。
さらに、「言語聴覚士の雇用を2025年までに増やす予定か」との質問に対する回答は、「現状のまま」が22.4%で、「増やす」が33.7%。「減らす」と答えた施設はわずか0.2%でした。こうしたデータや日本における高齢化率の上昇を踏まえれば、言語聴覚士の需要は、今後も高まっていくと考えて良さそうです。
言語聴覚士の求人を探す
資格以外に必要とされる能力
言語聴覚士は、患者さま、利用者さまやそのご家族に寄り添い、医師や看護師などと連携を取りながらリハビリを行う必要があります。
なお、言語聴覚士がサポートを行う主な障害として、以下の3タイプが挙げられます。
| 対象者 | 症状 | サポート内容 | |
|---|---|---|---|
| 言語障害 | ・高度機能障害のある方 ・言語発達障害のある子ども |
・正しい発音ができない ・なめらかに話せない |
・呼吸法の指導 ・読み書きの訓練 |
| 音声障害 | ・声帯に病変がある方 ・声帯を損傷した方 |
・発声が困難 | ・発声訓練 |
| 嚥下障害 | ・筋力が低下した方 ・神経や筋肉にまひがある方 |
・噛むことが困難 ・口からこぼれる ・むせる |
・食べ方の指導 ・口腔ケア ・食事介助 |
上記の業務に携わる際、言語聴覚士に共通して求められるスキルが、コミュニケーション能力です。
障害を抱える方が、スムーズに言葉を話したり、食べ物をのみこんだりできない自分自身の状態に、不安や苛立ちを感じるのは当然のことです。ときには、そうしたネガティブな気持ちが、体の動きをさらに妨げてしまったり、リハビリを拒否する事態につながったりすることもあります。
だからこそ言語聴覚士は、患者さま、利用者さまはもちろん、そのご家族とも十分にコミュニケーションを取り、信頼関係を築く必要があります。また、医師や看護師、理学療法士、作業療法士などと連携を図るためにも、コミュニケーション能力は欠かせません。
指導や訓練がうまくいかない場合は、別のプランを提案したり、粘り強くサポートしたりすることになるため、柔軟性や忍耐力が求められる場面もあるでしょう。
現役言語聴覚士にインタビュー
まとめ
言語聴覚士が働く場所は、医療機関や高齢者向けの介護福祉施設、障害を持つ子どもをサポートする特別支援学校など、多岐にわたります。業務内容は勤務先によって異なりますが、病気や事故、発達上の問題で言葉によるコミュニケーションが難しい方、あるいは食べたり飲み込んだりすることがうまくいかない方をサポートするのが、言語聴覚士の主な役割です。
施設によっては相談業務や事務などを任せられることもあるため、就職・転職時は求められるスキルや業務内容を事前に確認しておきましょう。
キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)
職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する
監修者プロフィール

マイナビコメディカル編集部
リハ職・医療技術職・栄養士のみなさまの転職に役立つ情報を発信中!
履歴書や職務経歴書の書き方から、マイナビコメディカルサイト内での求人の探し方のコツや、転職時期ごとのアドバイス記事などを掲載。
転職前の情報収集から入職後のアフターフォローまで、転職活動の流れに添ってきめ細やかなフォローができる転職支援サービスを目指しています。