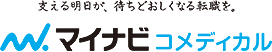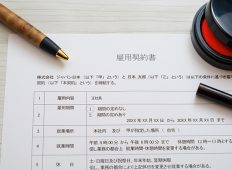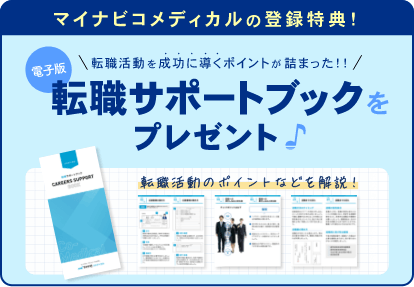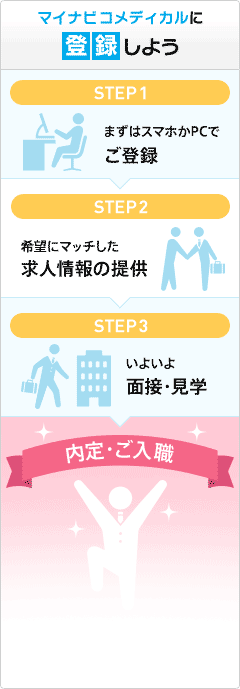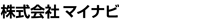臨床検査技師になるには?条件や国家試験・活躍の場について徹底解説!
臨床検査技師は、国家資格を必要とする医療専門職の1つです。医師は、血液検査や超音波検査などのデータをもとに患者さまの治療方針を決定しますが、その際、医師の指示に従って、患者さまの血液や尿、脳波などを検査するのが臨床検査技師です。
また、近年は医師や看護師をはじめ、複数の医療専門職が連携して診療を行う「チーム医療」が推進されており、検査のスペシャリストである臨床検査技師も、医療チームになくてはならない存在となっています。そのため、医療の現場では臨床検査技師に対するニーズが高まっており、資格取得を目指す方も増加傾向にあります。
この記事では、臨床検査技師になるために必要な条件、国家試験の難易度、合格率、求められる能力などについて紹介します。臨床検査技師を目指している方はもちろん、臨床検査技師として転職を考えている方も、ぜひ参考にしてください。
お気軽にご相談ください♪(完全無料)

目次
臨床検査技師とは?
臨床検査技師とは、医師の指示のもとで病気の診断や治療に必要な臨床検査を行い、検査結果を提供する医療専門職です。臨床検査技師は、「臨床検査技師等に関する法律」により規定されている国家資格であり、主に病院やクリニック、健診センターなどで活躍しています。
医療機関では、患者さまに対する適切な診断や治療が求められるため、多種多様な検査を行い、病気の早期発見・予防に努める臨床検査技師の存在は非常に重要です。臨床検査技師は、検査だけでなく医師と患者さまをつなぐ役目も担っていることから、臨床現場に欠かせない職種だといえるでしょう。
(出典:職業情報提供サイト(日本版O-NET)「臨床検査技師」/https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/161)
(出典:e-GOV「臨床検査技師等に関する法律」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC1000000076)
臨床検査技師が行う検査とは?
臨床検査技師が行う検査には、検体検査と生体検査があります。それぞれの詳しい内容は以下の通りです。
<検体検査>
検体検査では、患者さまから採取した血液や尿、組織細胞などの検体を用いて検査を行います。検体検査には下記のような種類があります。
| 一般検査 | 尿や便、胸水、腹水といった体腔液、髄液などの成分を調べる検査です。それによって、腎臓、肝臓、消化器の異常や感染症の有無などを鑑別できます。 |
|---|---|
| 生化学的検査 | 血清や尿に含まれるたんぱく質、脂質、糖質、腫瘍マーカーなどを測定・分析して、体調の変化や臓器の異常を検査します。 |
| 血液学的検査 | 血液に含まれる白血球、赤血球、血小板などの数や形態、機能を調べることで、貧血や炎症といった体内の異常や病態を検査します。 |
| 輸血・造血幹細胞移植 関連検査 |
輸血を行うために、血液型検査や交差適合試験(輸血する血液製剤と、患者さまの血液が適合するかどうかを調べる検査)などを行います。 |
| 微生物学的検査 | 患者さまから採取した喀痰や尿、便、咽頭ぬぐい液を培養し、感染症の原因となる細菌やウイルスなどを特定する検査です。あわせて、薬に対する感受性も検査します。 |
| 免疫血清学的検査 | 抗原に対する抗体反応を利用して、血中に含まれる抗体の有無や量を調べる検査です。感染症やがんの診断を行う際に実施します。 |
| 病理・細胞診検査 | 患者さまから採取した臓器や細胞の組織を観察し、がん細胞をはじめとする悪性細胞がないかを検査します。 |
| 遺伝子・染色体検査 | 遺伝子や染色体を調べる検査です。生まれつきの体質や病気のリスク、出生後に生じた遺伝子の変化などを調べ、病気の診断を行います。近年では治療薬の有効性や治療効果の予測にも応用されています。 |
<生体検査>
生体検査とは、心電図検査や脳波検査、超音波など、患者さまの体を直接調べる検査のことです。生体検査には下記のような種類があります。
| 心電図検査 | 心電図、心音図、脈波などを検査して、脈の乱れや心臓の病気の有無などを調べる検査です。 |
|---|---|
| 脳波検査 | 頭皮に電極を装着し、脳の電気信号を記録することで、腫瘍や外傷、血管の異常などを調べます。 |
| 超音波検査 | 超音波を用いて体内の組織を画像化する検査で、臓器、血管の観察や胎児の状態を調べる際に行います。 |
| MRI検査 | 磁気の力を利用したトンネル状の装置を使って体の断面図を撮影し、病巣を調べる検査です。 |
| 眼底写真検査 | 眼底カメラ・眼底鏡を用いて瞳孔の奥にある眼底を観察する検査です。目の病気や生活習慣病の早期発見に有効とされています。 |
| 熱画像検査 | 皮膚の表面温度を測定し、血行障害や皮膚疾患などを調べる検査です。 |
| 呼吸機能検査 | 肺活量、肺機能などを検査して、肺や気管、気管支における病気の有無を調べます。 |
| 聴力検査 | いろいろな周波数の音を使って、耳の聞こえを調べる検査です。 |
| 味覚・嗅覚検査 | 味覚や嗅覚の感度を調べる検査です。 |
(出典:一般社団法人日本臨床衛生検査技師会「臨床検査技師の紹介」/https://www.jamt.or.jp/target/general/introduction/)
臨床検査技師になるための「3つの条件」
臨床検査技師になるには、主に3つの条件があります。高校卒業後、下記のどれか1つを満たしていれば、臨床検査技師の国家試験を受けることができます。
| 文部科学大臣が指定した大学を卒業する |
|---|
| 3年制短期大学の臨床検査学科などで、所定の臨床検査技師養成過程を修了すると、臨床検査技師国家試験の受験資格が得られます。 |
| 厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所(専門学校)を卒業する |
|---|
| 厚生労働大臣や都道府県知事が指定した、3・4年制の専門学校で専門過程を修了すると、臨床検査技師国家試験の受験資格が得られます。 |
| 大学で指定された課程を終了する |
|---|
| 医学・歯学系の正規過程修了、または保健学系・獣医学系・薬学系の学部で所定の過程を修了すると、臨床検査技師国家試験の受験資格が得られます。 |
臨床検査技師養成所や大学に入学するための主な受講科目(選択科目を含む)として、数学、生物、化学、物理などが挙げられます。必要な科目については、高校時代に履修しておくとよいでしょう。
【大学or専門学校】それぞれのメリット・デメリット
臨床検査技師を目指すにあたっては、どの学校を選ぶべきか迷う方も多いでしょう。ここでは、大学と専門学校それぞれのメリット・デメリットを比較しておきます。ぜひ参考にしてください。
<大学>
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・附属病院やクリニックを持っているケースが多く、充実した実習を行える ・研究機関を備えた大学の場合、先端の医療機器に触れられる ・医療機関の他、大学の研究室や企業の研究所などでも働くことができ、将来のキャリアが広がる ・学士号を取得できる |
・卒業までに4年かかり、医療現場に出るのが短大、専門学校よりも遅くなる ・大学によっては国家試験の合格率が低いところもある |
<専門学校>
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・3年で卒業して国家試験に合格すれば、大学進学者よりも早くから現場に出られる ・大学よりも入学しやすいことが多い |
・短期間で基礎から実習までのカリキュラムをこなす必要があり、やや過密な学習スケジュールになる ・一度入学すると進路変更が難しく、変更したい場合は再度他の学校に入学しなければならない |
大学・専門学校には、それぞれメリット・デメリットがあると理解した上で、自身の考え方やキャリアプランに適した学校を選ぶことが重要です。
臨床検査技師の最大の難関!「臨床検査技師国家試験」について
決められた学校を卒業するだけでは、臨床検査技師という職業に就くことはできません。臨床検査技師になるには、大学・専門学校規定の過程を修了した後に、臨床検査技師国家試験に合格する必要があります。
臨床検査技師の国家試験は、毎年2月に行われます。試験は日本各地(北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・香川・福岡・沖縄)で行われるため、どの地域に住んでいる方も比較的受験しやすいといえるでしょう。
筆記試験は、下記の専門科目から1問1点で200問出題されます。
・公衆衛生学(関係法規を含む)
・臨床検査医学総論(臨床医学総論および医学概論を含む)
・臨床検査総論(検査管理総論および医動物学を含む)
・病理組織細胞学
・臨床生理学
・臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む)
・臨床血液学
・臨床微生物学および臨床免疫学
(出典:厚生労働省「臨床検査技師国家試験の施行」/https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukensagishi/)
臨床検査技師国家試験の難易度と合格率
先に紹介したように、臨床検査技師の国家試験は、年に1回、2月に日本各地の指定された場所で行われます。なお、臨床検査技師国家試験の合格基準は200点満点中120点以上となっています。
国家試験と聞くと「難易度が高い」と感じる方が多いかもしれませんが、授業や実習などに真摯に取り組み、知識と技術をきちんと習得していれば、合格の道は開けるでしょう。以下は、厚生労働省が公開している臨床検査技師国家試験の受験者、合格者、合格率のデータです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 全体 | 4,829人 | 3,828人 | 79.3% |
| (うち新卒者) | 3,948人 | 3,572人 | 90.5% | |
| 2019年 | 全体 | 4,816人 | 3,828人 | 75.2% |
| (うち新卒者) | 4,002人 | 3,462人 | 86.5% | |
| 2020年 | 全体 | 4,854人 | 3,472人 | 71.5% |
| (うち新卒者) | 3,940人 | 3,273人 | 83.1% | |
| 2021年 | 全体 | 5,115人 | 4,101人 | 80.2% |
| (うち新卒者) | 3,947人 | 3,614人 | 91.6% | |
| 2022年 | 全体 | 5,331人 | 3,729人 | 75.4% |
| (うち新卒者) | 4,408人 | 3,537人 | 86.4% | |
| 2023年 | 全体 | 5,002人 | 3,880人 | 77.6% |
| (うち新卒者) | 4,010人 | 3,589人 | 89.5% |
(出典:厚生労働省「第64回臨床検査技師国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2018/siken07/about.html)
(出典:厚生労働省「第65回臨床検査技師国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2019/siken07/about.html)
(出典:厚生労働省「第66回臨床検査技師国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2020/siken07/about.html)
(出典:厚生労働省「第67回臨床検査技師国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2021/siken07/about.html)
(出典:厚生労働省「第68回臨床検査技師国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2022/siken07/about.html)
(出典:厚生労働省「第69回臨床検査技師国家試験の合格発表について」/https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2023/siken07/about.html)
合格率は例年70~80%前後で推移しており、新卒の場合は85~90%ほどの合格率となっています。
これらのデータからも分かるように、臨床検査技師の国家試験に合格するのはけっして困難ではありません。卒業見込みの時点で国家試験に合格できるように、大学や専門学校に在学している間は必要な知識・技術の習得に励みましょう。
臨床検査技師の就職先
臨床検査技師の資格を取得した後は、病院やクリニックのほか健診センター、臨床検査センター、医療機器メーカーなどさまざまな場所で活躍できます。
ここでは、臨床検査技師が活躍する就職先について解説します。
病院・クリニック
病院における臨床検査技師の主な仕事は、医師の指示のもとで入院・来院する患者さまの身体状態を検査(検体検査・生体検査)することです。病院には複数の診療科がそろっているため、幅広い検査技術を身に付けられるでしょう。なお、病院勤務では急患による臨時の検査が発生することもあるため、そうした場面では冷静かつ正確に対応することが求められます。
一方、クリニックでは、検体検査を臨床検査センターに外注するケースが多いため、臨床検査技師の業務内容は生体検査が中心です。ただし、臨床検査センターに検体を送るために、採血などの検体採取業務を実施することはあります。
また、クリニックで働く臨床検査技師は、それぞれの診療科に関連する生体検査が多い点に特徴があります。例えば、呼吸器系を専門とするクリニックであれば呼吸機能検査、消化器系を専門とするクリニックの場合は、腹部エコーなどの業務が多くなるでしょう。そうしたことから、クリニックへの就職・転職では、専門分野を持っている臨床検査技師が有利だといわれています。
健診センター
健診センターは、病気の予防や早期発見、健康維持を目的に、健康診断や人間ドック、PET検診などを行う施設です。健診センターで働く臨床検査技師は、身長・体重の測定や視力・聴力検査、血圧測定などに加えて、心電図、採血、超音波検査といった幅広い業務に携わります。
効率的に多くの受診者さまに対応する必要があるため、健診センターでは担当制で検査業務を行うケースが多くみられます。また、乳腺・腹部エコーなどの検査では女性担当者のニーズが高いことから、女性臨床検査技師が多く働いているのも特徴の1つです。
病院に比べて、日々多くの生体検査を行うので、生体検査を中心に行いたい方や病気の早期発見にやりがいを感じる方には、おすすめの職場といえるでしょう。
臨床検査センター
臨床検査センターは、病院やクリニックから送られた検体の検査を行う施設です。臨床検査センターでは、血液や尿といった通常の検体検査だけでなく、遺伝子検査、腫瘍マーカー検査、アレルギー検査、内分泌検査など数多くの検査を行います。病院では行えないような特殊な検査を実施することもあるため、臨床検査センターで働く臨床検査技士は、幅広く専門的な検査スキルが身に付くでしょう。
大手の臨床検査センターの場合は、全国各地から検体が届くため、対応する検査の数は病院と比べて格段に多くなります。そのため、検査ごとに部門が分かれており、臨床検査技師が担当する検査項目も固定されているのが一般的です。
医療機器メーカー
医療機器メーカーで働く臨床検査技師は、アプリケーションスペシャリストとして活動します。主な業務は、医療機関に出向いて自社製品のプレゼンテーションを行ったり、営業職のサポートをしたりすることです。定期的に顧客である医療機関を訪問し、医療機器の使い方の説明、フォローなどを行うため、臨床検査技師として医療機器を扱ってきた経験を存分に生かせるでしょう。
なお、医療機器メーカーの場合、病院やクリニックなどの医療機関で働くよりも給与が高い傾向にあります。加えて、年間休日などの福利厚生が充実した職場が多いのも特徴です。
治験コーディネーター
治験とは、製薬会社や医療機器メーカーが開発した、新規の医薬品や医療機器の安全性・有効性を確認するために行う臨床試験のことです。そして、治験を行う際に患者さまと医療機関、製薬会社の間に立ち、スムーズな進行をサポートするのが、治験コーディネーターの役割です。
臨床検査技師は検査のスペシャリストであり、検査値の変動や異常値への見識があることから、治験を安全かつ円滑に行うために必要とされています。主な仕事内容は患者さまのケアやサポートですが、現場では治験内容の説明だけでなく、ストレスを軽減するための相談相手も務めます。
その他、治験業務フローの作成や治験担当医の補助、関係者への連絡調整などの業務も担当するため、やりがいは大きいでしょう。
臨床検査技師の将来性は?
近年は健康志向が高まり、病気を未然に防ぐための予防医学が注目されています。そうしたなか、多くの人が生活習慣病やがんの早期発見のために健康診断を受けるようになり、予防や早期発見を目的とした各種検査に対するニーズは、以前よりも高くなりました。
また、医療の高度化が進む現代において、より質の高い医療を提供するためには、各種検査にも高い精度と熟練した技術が求められます。
そうした点を踏まえるなら、検査業務全般を担う臨床検査技師は、医療の現場に欠かせない存在であり、将来性のある職種だといえるでしょう。
加えて、病院・クリニックといった医療機関以外にも、臨床検査技師の活躍の場が広がっているため、経験を積み専門性を蓄積していけば、臨床検査技師として長く活躍し続けられるはずです。
勉強だけではない?臨床検査技師に求められる能力とは
臨床検査技師の業務を行うにあたっては、専門分野の知識・技術が身に付いていることが大前提ですが、それだけで十分とはいえません。
近年は、チーム医療の一員として治療に携わることも増えているため、臨床検査技師には他職種と連携できる協調性やコミュニケーション能力、データの正確な分析力、向上心・探究心などさまざまな能力が求められます。
ここからは、臨床検査技師に求められる能力の詳細をご紹介します。
協調性・コミュニケーション能力
臨床検査技師はチーム医療において、医師や看護師をはじめとする医療専門職と連携し、患者さまの治療・ケアを支える役割を担います。
そのため、検査についての高い専門性はもちろん、他職種とスムーズに協力し合える「協調性」や「コミュニケーション能力」も、臨床検査技師にとって不可欠な能力といえるでしょう。
また、臨床検査技師は治験コーディネーター(CRC)として活躍するケースもあり、その場合は製薬会社の臨床開発モニター(CRA)や、治験を担当する医師、関係部署、被験者となる患者さまと連携しながら仕事を進めることになります。そうした際にも、協調性やコミュニケーション能力は非常に重要となるでしょう。
分析力
患者さまの治療・ケアにおいて、医師は臨床検査技師が提示したデータをもとに診断を行い、治療方針を決定します。したがって、臨床検査技師には検体検査や生体検査を行うための知識・スキルだけでなく、検査によって得られたデータを正確に分析する能力が求められます。
加えて、専門性の高い医療機器や顕微鏡を使った検査、標本の制作など細かい作業を行う機会が多いのも臨床検査技師の特徴です。そうしたことから、臨床検査技師には細心の注意を払いつつ、正確に作業を遂行できる能力も必要とされます。
向上心・探求心
新しい医療機器や検査方法が次々に開発されるなど、臨床検査の分野は日々進歩しています。そのなかで技術の進歩に対応し、検査の結果を正しく判断するには、医学や生命科学に関する幅広い知見と、常に新たな知識や技術を得ようとする向上心・探求心が必要です。加えて、進化する医療機器を柔軟に使いこなせる適応力も、臨床検査技師の大事な能力といえるでしょう。
ただし、ここで紹介した協調性やコミュニケーション能力、分析力、向上心・探求心がすべてそなわっていないと、臨床検査技師になれないというわけではありません。
臨床検査技師を目指して勉強したり、医療機関に勤務して経験を積んだりするなかで、さまざまな能力を身に付け、磨いていくことは十分に可能です。「臨床検査技師になりたい」という意志がある方は、積極的にチャレンジしてみましょう。
まとめ
臨床検査技師は国家資格が必要な専門職であり、臨床検査技師を目指すにあたっては、大学や専門学校で規定の過程を修了し、国家試験を受ける必要があります。
医療の高度化・複雑化が進む現代では、医師や看護師をはじめ、複数の医療職が連携して治療やケアを行う「チーム医療」が注目されており、検査のプロである臨床検査技師も医療チームに不可欠な存在です。
そうしたことから、臨床検査技師には専門知識・スキルだけでなく、他職種との連携を取るコミュニケーション能力や医療全般についての幅広い知見、日々の勉強を怠らない向上心など、さまざまな能力が求められます。どのような臨床検査技師になりたいかを考え、夢を膨らませながら、着実に臨床検査技師としての経験を重ねていきましょう。
キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)
職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する
※当記事は2023年12月時点の情報をもとに作成しています
監修者プロフィール

マイナビコメディカル編集部
リハ職・医療技術職・栄養士のみなさまの転職に役立つ情報を発信中!
履歴書や職務経歴書の書き方から、マイナビコメディカルサイト内での求人の探し方のコツや、転職時期ごとのアドバイス記事などを掲載。
転職前の情報収集から入職後のアフターフォローまで、転職活動の流れに添ってきめ細やかなフォローができる転職支援サービスを目指しています。