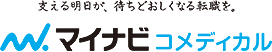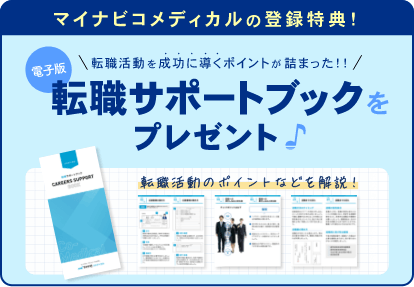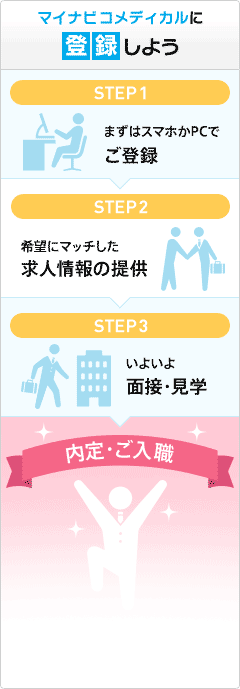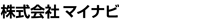胚培養士とは?仕事内容・就職先・必要な資格・需要も!
医療技術者には、診療放射線技師や臨床工学技師などのほかにも、さまざまな職種が存在します。なかでも、体外受精や受精卵の凍結、融解、培養に携わる不妊治療の専門職として注目が高まっている職種が、「胚培養士(はいばいようし)」です。
近年は晩婚化が進み、不妊に悩む方も増えてきました。だからこそ、不妊治療のスペシャリストでもある胚培養士の需要が増えているのです。
今回は、胚培養士の仕事内容、胚培養士になる方法、胚培養士のやりがいなどを詳しく解説します。産婦人科領域の専門職に興味を持つ方や、コメディカル職に関心を持つ方は、参考になさってください。
転職のプロと考えていきましょう!(完全無料)

目次
胚培養士とは?仕事内容と活躍の場
胚培養士は、医師の指導のもとで体外受精や高度生殖補助医療(ART)をサポートする、不妊治療のスペシャリストです。産婦人科領域の知識はもちろん、デリケートな精子、卵子を扱える高度な技術を身に付けた胚培養士は、別名「エンブリオロジスト」とも呼ばれています。
他のコメディカル職に比べて活躍の場こそ限られますが、胚培養士は「生命の誕生をサポートする」という大事な役割を担った専門職です。ここでは、胚培養士の仕事内容と活躍フィールドを解説しましょう。
胚培養士の仕事内容
「胚培養」とは、体外に取り出した自然受精の難しい精子と卵子を培養し、胚に育てることです。その言葉からもわかるように、体外で精子と卵子を授精させ、母体に戻すまでの過程で胚の凍結や融解、培養などを行うことが胚培養士の主な仕事内容となります。胚培養士は、その他に検卵、精液の採取・検査、精子の選別・処理といった業務も行います。
ただし、卵子の採取や受精した胚の移植については、医師免許がないと行えません。そのため胚培養士は、基本的に医師の指導のもとで一つひとつの仕事を進めることになります。
胚培養士の就職先
胚培養士の一般的な就職先は、不妊治療を行う病院やクリニック、不妊治療センターです。
とはいえ、胚培養士のサポートが必要な体外受精や高度生殖補助医療(生殖医療)は、認められた施設でしか行うことができません。胚培養士が活躍できるのは、不妊治療を行う病院、クリニック、不妊治療センターのなかでも、高度生殖補助医療の認可を受けた施設に限られることを覚えておきましょう。
また、病院やクリニック、不妊治療センターだけでなく、動物の胚細胞を使用した実験を行う研究機関も胚培養士の就職先の一つです。ちなみに、動物の卵子の採取や胚移植は、医師免許がなくても行うことができます。
求人の特徴・将来性・年収アップのポイントも
胚培養士になる方法は?代表的な認定資格も
胚培養士になるために必須の学歴や資格はありません。しかし、胚培養士には高い知識や技能が必要とされるため、一定以上の学歴や経験、知識がなければ働くことができない職場も増えています。
胚培養士を目指す場合は、下記3つのいずれかの方法を選ぶのが一般的です。
- ・看護師や臨床検査技師などの医療職、コメディカル職を経験した後に目指す
- ・動物学部・生物学部などで生殖機能の研究経験を重ね、卒業した後に目指す
- ・胚培養士の養成機関を卒業した後に目指す
専門的な知識と技術を身に付け、即戦力として活躍するためには、最初に挙げた「看護師や臨床検査技師などを経て胚培養士となる方法」がいちばんのおすすめです。実際に、胚培養士の多くが臨床検査技師としても活躍しています。
胚培養士には必須となる資格がないものの、日々の業務や就職・転職に役立つ認定資格は存在します。ここからは、代表的な認定資格である「認定臨床エンブリオロジスト」「生殖補助医療胚培養士」「生殖補助医療管理胚培養士」の3つを詳しく紹介しましょう。
具体的な仕事内容から向いている人まで徹底解説!
認定臨床エンブリオロジスト
認定臨床エンブリオロジストとは、「日本臨床エンブリオロジスト学会」が主催する認定資格で、エンブリオロジストの知識・技術の向上を目的としています。
認定臨床エンブリオロジストの資格を取得するには、まず日本臨床エンブリオロジスト学会の会員になり、定められた経験を積んだ上で試験に合格する必要があります。なお、認定臨床エンブリオロジストの資格は5年ごとの更新が必要です。
| 対象者 | ・日本臨床エンブリオロジスト学会の会員である ・生殖補助医療業務に1年以上従事している ・定められた学歴に該当している ・日本臨床エンブリオロジスト学会が主催するワークショップに参加し、修了証の交付を2回以上受けている |
|---|---|
| 試験日 | 年1回 |
| 試験内容 | 筆記試験・DVD提出による実技試験・面接試験 |
| 審査受験料 | 30,000円 |
(出典:日本臨床エンブリオロジスト学会「認定資格受験・更新」/https://embryology.jp/certification/)
生殖補助医療胚培養士
生殖補助医療胚培養士とは、「一般社団法人日本卵子学会」が、生殖補助医療に携わる胚培養士の水準向上を目的に創設した認定資格です。
生殖補助医療胚培養士の資格を取得するには、まず日本卵子学会の会員になり、定められた要件を満たした上で試験に合格する必要があります。なお、生殖補助医療胚培養士の資格は5年ごとの更新が必要です。
| 対象者 | ・日本卵子学会の会員である ・生殖生物学関連科目を修得した臨床検査技師または看護師である ・指定の学部で生殖生物学関連の単位を修得している ・認定施設において1年以上の臨床実務経験がある ・直近1年以内に日本卵子学会が主催する講習会・学会大会に参加している |
|---|---|
| 試験日 | 年1回 |
| 試験内容 | 書類審査・筆記試験・面接試験 |
| 審査受験料 | 60,000円(講習会受講料30,000円/審査料30,000円) |
(出典:日本卵子学会「ヘッドライン詳細/要項/規程」/https://jsor.or.jp/embryologist/rule.html)
生殖補助医療管理胚培養士
生殖補助医療管理胚培養士とは、「一般社団法人日本卵子学会」と「一般社団法人日本生殖医学会」が共同で創設した認定資格です。生殖補助医療胚培養士の上位資格であり、より高度な知識・技術を持つ胚培養士の証明となります。
生殖補助医療管理胚培養士の資格を取得するためには、まず生殖補助医療胚培養士資格の取得が必須です。また、日本卵子学会と日本生殖医学会の会員になり、定められた厳しい要件を満たした上で試験に合格する必要があります。なお、生殖補助医療管理胚培養士の資格も、5年ごとの更新が必要です。
| 対象者 | ・日本卵子学会と日本生殖医学会の会員 ・博士の学位を取得し、生殖に関わる論文を発表している ・一定期間において、該当の学会に定められた回数参加している |
|---|---|
| 試験日 | 年1回 |
| 試験内容 | 筆記試験・口述試験 |
| 審査受験料 | 30,000円 |
(出典:日本生殖医学会「生殖補助医療管理胚培養士制度細則」/http://www.jsrm.or.jp/document/seishoku_haibaiyou.pdf)
胚培養士の需要
近年では、少子化、晩婚化、高齢出産の増加などの影響で、不妊治療のニーズが高まっています。また、女性の社会進出が進めば、そうした問題は今後さらに増加すると推測されます。そのため、高度な専門知識やスキルを持つ胚培養士の需要も、社会情勢に比例して高まると考えて良いでしょう。
なお、現在は厚生労働省でも不妊治療に関する支援などの取り組みが進められており、公式ホームページで公表されているデータによると、「不妊に悩む方への特定医療支援事業」の指定医療機関においては、胚培養士の配置が望ましいとされています。
(出典:厚生労働省「不妊治療に関する取組」/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/funin-01.html)
(出典:厚生労働省「実施医療機関の基準比較」/https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000314vv-att/2r985200000314zc.pdf)
(出典:厚生労働省「不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件に関する指針」/https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000697079.pdf)
また、ここ数年は体外受精や胚移植・顕微授精などの高度生殖補助医療を経て生まれた子ども(ART出生児)についても増加傾向にあります。こうしたデータからも、胚培養士の需要が高まることは明らかでしょう。
(出典:日本産科婦人科学会「ARTデータブック」/https://www.jsog.or.jp/modules/committee/index.php?content_id=12)
転職のプロがアドバイスします♪(完全無料)
胚培養士のやりがい
「不妊治療になくてはならない存在」ともいえる胚培養士は、生命の誕生をサポートする重要な役割を果たすことから、大きなやりがいを感じられる仕事となっています。特に、患者さまの思いを身近で感じ取り、徹底したサポートを行い、妊娠された時の喜びを共有できるのは、胚培養士だからこその魅力です。
しかし、不妊治療は必ず成功するわけではありません。どれだけ慎重に不妊治療にあたっても、うまくいかないケースはあります。そして、そのたびに患者さまの悲しい顔を見ることは、胚培養士にとってもつらい経験となるでしょう。
それらの点を踏まえて考えると、胚培養士に向いているのは下記のような方です。
- ・細かく、かつ慎重な作業を続けていても苦にならない
- ・患者さまの気持ちに寄り添える
- ・努力が実らなくても、落ち込みすぎない
胚培養士は大変な面もありますが、現在、そしてこれからの社会に必要とされる重要な職業といえます。他の職業では感じられないやりがいや喜びもたくさんあるため、「不妊に悩む家族をサポートしたい」「少子化などの社会問題に向き合いたい」と感じている方は、胚培養士を目指してみてはいかがでしょうか。
「マイナビコメディカル」では、胚培養士求人や臨床検査技師求人をはじめとしたあらゆるコメディカル職の求人情報を掲載しています。職場によって採用条件や募集要項、待遇などが異なるため、ご自身に合った求人を見つけるためにも、マイナビコメディカルをぜひご利用ください!
臨床検査技師の求人を探す
まとめ
胚培養士とは、体外受精や生殖補助医療(ART)をサポートする不妊治療のスペシャリストです。「エンブリオロジスト」とも呼ばれるこの職業は、病院やクリニック、不妊治療センターが主な就職先となります。
胚培養士になるために必須の学歴や資格はありませんが、高度な技術や知識が必要とされることから、認定資格を取得しておくのがおすすめです。また、少子化、晩婚化、高齢出産の増加などの影響で、不妊治療のニーズが高まっていることから、胚培養士の需要もますます増えていくと予想されます。
コメディカル分野の求人サイト「マイナビコメディカル」では、胚培養士が活躍できる求人を数多く掲載しています。業界に精通したキャリアアドバイザーによる無料転職サポートの提供や、非公開求人の紹介も行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)
職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する